ざっくり要約!
- 家を貸すことで賃料収入が得られる一方、赤字や資産価値低下、金利上昇、トラブル発生などのリスクがある
- 「普通借家契約」と「定期借家契約」のどちらが適しているかは、貸したい期間や得たい収入による
- 管理方法は「自主管理」「管理委託」「サブリース」の3つに大別される
持ち家から転居するときには、売却のみならず、賃貸に出すことも選択肢の1つとなります。家を貸すメリットは、賃料収入が得られるとともに、再び住むことができることです。しかし、賃貸経営にはリスクも伴うため、よく理解したうえで検討するようにしましょう。
本記事では、家を貸すメリット・デメリットとともに、手順や注意点を解説します。
記事サマリー
使っていない家は貸すべき?
転勤や親との同居などで空いた家、または相続で手に入れた家を有効活用する選択肢の一つとして、その家を賃貸に出すことが考えられます。家を貸し出すことには、家賃収入を得られる利点や、将来自分が再びその家に戻る選択肢を保持できるというメリットがあります。しかし、家を貸し出す際にはいくつかの注意点を把握しておくことが必要になります。
「家を貸出す流れは?」「気を付けるべきポイントは?」など、様々な疑問を感じている方も多いのではないでしょうか?この記事では、家を賃貸に出す際のメリットと注意点、賃貸物件としての管理方法やかかるコスト、賃貸ビジネスを成功させるためのポイントについて詳しく解説します。
家を貸すメリット
まずは、一戸建てやマンションを貸し出すメリットを整理しておきましょう。
家賃収入が得られる
持ち家を貸すことによって得られる賃料は、家計や老後資金の足しになります。中には、不動産投資だけで生計を立てている投資家もいるほどです。資産の形成方法は数あれど、不動産投資のように比較的安定していて、ある程度の利回りが得られる投資方法は多くはありません。
また住むことができる
転勤や海外転勤に際し、自宅を売るか、あるいは自宅を賃貸に出すか、空き家にしておくか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。売却すれば、当然ながら今後、自身や家族が住むことはできません。また、空き家にしておくと維持費の負担が大きくなるでしょう。一方で、一時的でも家を貸し出せば、また自身や家族が住むことができるとともに、空き家を有効活用できます。
・「リロケーション」に関する記事はこちら
リロケーションとは?転勤時の空き家活用で検討したい賃貸方法をご紹介
家の劣化を防ぐことにもつながる
買った家を賃貸に出すことで、家の劣化を防ぐ効果も期待できます。通常、家が長期間使用されないと、様々な部分が劣化しやすくなります。特に、換気が行われないことで湿気が溜まり、カビが生えたり、木部が腐食したりするリスクが高まります。しかし、家を誰かに貸し出して住んでもらうことで、定期的に換気や掃除が行われ、これらの問題をある程度防ぐことができます。
さらに、入居者が日常的に生活することで、小さな修繕が必要な箇所に早期に気づきやすくなり、大規模な修繕が必要になる前に対処できることも大きなメリットです。これにより、家賃収入を得るだけでなく、物件の長期的な価値を維持しやすくなります。
東急リバブルの「賃貸管理サービス」はこちらから
家を貸す契約方法は2種類ある
家を貸す方法は「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つです。どちらが適しているかは、貸したい期間や必要とする収入などによります。
普通借家契約
普通賃貸借契約の契約期間は2年間が一般的です。借主(入居者)が賃貸借契約の継続を希望する場合、貸主は原則的に契約更新を行います。普通賃貸借契約の注意点は、貸主が契約を解除したい場合は、正当な理由が必要なため、貸主の都合で所有物件に戻ることが難しいところです。正当な理由があれば6か月前の解約予告により戻ることができますが、実際にはなかなか正当な理由として認められず、借主からの解約希望があるまでは所有物件に戻れない可能性が高くなります。
定期借家契約
定期借家契約は、貸主が契約期間を自由に設定でき、更新はありません。そのため転勤の間だけ貸したい、といった場合には、定期賃貸借契約がおすすめです。なお、貸主と借主が合意すれば新たな契約条件で再契約することが可能です。
ただし、この契約形態は、長期的に住みたいと考える入居者にとっては不向きであり、短い契約期間の場合、相場よりも家賃を低く設定しないと借り手を見つけにくい傾向があります。また賃料滞納リスクが低いとされる大手法人の社宅契約では、法人の規定で定期賃貸借での契約ができないことがあるので注意が必要です。
2種類の契約方法の特徴まとめ(表)
以下は、「普通借家契約」と「定期借家契約」の主要な特徴を詳細に説明した表です。
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
| 契約期間 | 普通借家契約では、一般的に「2年間」とすることが多いです。 | 自由に設定できます。 |
| 契約更新 | 更新が前提となります。(正当事由がない限り、貸主からの更新拒絶はできません。) | 更新はございません。(貸主と借主の合意により再契約できます。) |
| 貸主からの解約 | 解約の申し入れには6ヶ月前の予告および、正当事由が必要です。借地借家法上、正当と認められる事由がない限り借主に対して解約の申し出を行っても、建物の明け渡しは受けられません。 | 原則、契約期間中の解約はできません。 |
| 借主からの解約 | 契約に応じた期間の事前通知によって可能となります。 | 契約に応じた期間の事前通知によって可能となります。 |
以上のように普通賃貸借契約と定期賃貸借契約には契約期間や注意点などに違いがあります。「どちらが自分に適しているのか不安」という方は、不動産会社に相談するのがおすすめです。
賃貸住宅の管理方法は3種類ある
家を貸す際には、賃貸借契約の種類だけでなく、管理方法も検討しなければなりません。管理方法は、次の3つに大別されます。
自主管理
解説
自主管理は、オーナーが直接、自己の賃貸物件の管理を行う方法です。外部に委託せず、すべての管理業務を自身で行います。
委託費用や手数料はかかりませんが、賃貸経営では次のようにやるべきことが多岐に渡ります。
- 入出金管理
- 修繕・メンテナンスとその管理や手配
- 入居者募集・審査
- 賃貸借契約
- 更新契約
- 退去立会い
- 確定申告 など
メリット
自主管理の主な利点は、管理手数料が不要であるため、得られる家賃収入が最大化されることです。また、物件への対応が迅速に行えるため、入居者からの評価が高まる可能性もあります。
注意点
しかし、自主管理での管理業務は非常に手間がかかるため、本業があるオーナーにとっては時間的な負担が大きくなりがちです。また、専門的な知識が求められる場面も多く、その準備と対応には相応の努力が必要となります。
管理委託
解説
管理委託とは、賃貸物件の管理を専門の不動産会社に依頼する方法です。管理手数料を支払って、日々の運営からトラブル対応までの管理業務を全てまたは一部委託します。遠方で物件を持っているオーナーや、管理業務の負担を減らしたい人にとって適した選択肢です。委託料は管理会社や委託する範囲によりますが、賃料収入の5%前後が一般的となっています。
メリット
管理委託の最大の利点は、煩雑な管理業務を自分で行う必要がなくなることです。不動産管理は専門知識が求められる場合が多く、これをプロに委ねることで、オーナーは他の業務や私生活に集中できます。特に、物件がオーナーの居住地から離れている場合、管理委託は非常に有効です。
注意点
管理委託には手数料が伴うため、その費用が家賃収入から差し引かれる点に留意が必要です。適切な不動産会社を選び、コストパフォーマンスをしっかり評価することが重要となります。
サブリース
解説
サブリースでは、不動産会社がオーナーから物件を借り上げ、それを再び他の借主に転貸します。この方式では、不動産会社が直接的な賃借人となるため、家賃収入の安定性が増します。手数料は賃料の10%程度と管理方法のなかで最も高額になりますが、経営負担を大幅に軽減できます。
メリット
サブリースの最大の利点は、安定した家賃収入と管理の簡便さです。不動産会社が全ての管理業務を担うため、オーナーは空室リスクや日々の運営に関する心配から解放されます。また、空室の際でも家賃収入が保証される場合が多いです。
注意点
しかし、サブリースでは家賃が市場価格より低く設定されることが多く、入居者から得られる一時金(礼金や更新料)も不動産会社が受け取るため、オーナーの手取りは減少します。また、契約によっては、退去時の修繕費用がオーナー負担となる場合もあります。
・「サブリース」に関する記事はこちら
サブリースとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説
東急リバブルの「リロケーションプラン」はこちらから
・「賃貸住宅の管理方法」に関する記事はこちら
賃貸管理とは?賃貸管理費・共益費・管理費の違いも説明
家を貸す流れ

家をスムーズに貸し出すためには、あらかじめその流れを把握しておくことが大切です。ここでは、家を貸し出すまでの一般的な流れを解説します。
1.不動産会社へ相談する
まずは、不動産会社に賃貸の相談をします。家賃や入居条件、依頼方法など、家を貸す具体的な条件を決めていきます。
2.入居者募集・申し込み・審査
貸出し条件が決まれば、入居者の募集を開始します。内覧を経て、物件を気に入ってくれた方から申し込みが入り次第、入居審査と続きます。
3.賃貸借契約
入居者が決まれば、契約の運びとなります。賃貸借契約では、不動産会社の仲介のもと、重要事項説明の読み合わせや契約書への署名・捺印などが行われます。
4.更新・解約
普通借家契約の場合は、解約まで更新契約を繰り返します。定期借家契約は、期間満了をもって契約終了となりますが、再契約は可能です。
・「家を貸す流れ」に関する記事はこちら
マンションや一戸建てを貸すときの流れ
家を貸す時に必要な税金や費用とは
税金
所得税
家賃収入は所得税の課税対象となります。物件を貸し出すことによって得られる収入は「不動産所得」として、年間の収入から必要経費を差し引いた額に対して所得税が課されます。
固定資産税及び都市計画税
所有する不動産には固定資産税と都市計画税が課税されます。これらは物件の価値に基づき毎年評価され、税額が決定されるため、物件の所有者はこれらの税金を年間を通じて支払う義務があります。
その他の費用
修繕費
物件の種類によって異なりますが、一般的に分譲マンションでは、管理組合への修繕積立金と管理費が必要です。これに対し、一戸建ての場合、大規模な修繕が必要になった際には、その費用はオーナーの負担となります。予期せぬ修繕が発生することも想定し、適切な資金計画を立てることが重要です。
管理手数料
不動産管理を委託する場合、管理業務を行う不動産会社には管理手数料が必要です。この手数料は通常、月額家賃の5〜10%程度とされ、管理サービスの内容によって異なります。
リフォーム費用・クリーニング代
物件を貸し出す前には、ハウスクリーニングや必要に応じてリフォームを行うことが一般的です。これには壁紙の張り替えや水回りの設備更新が含まれ、物件の魅力を保つために重要となります。
火災保険料
貸主は通常、建物や室内の補償を目的とした火災保険に加入します。これにより、火災やその他のリスクから物件を保護し、万が一の事態に備えます。
施設賠償責任保険料
物件から他人への損害が発生した場合、施設賠償責任保険がこれをカバーします。例えば、建物の一部が落下し第三者を傷つけた場合など、オーナーの負担を軽減します。
不動産会社への報酬
物件の募集や管理を不動産会社に依頼する際は、通常、契約成立時に家賃の1か月分相当の報酬を支払います。
原状回復費用
借主が退去する際の原状回復責任は、通常摩耗に関してはオーナーが負担します。この費用には、故意または過失による損傷が含まれないため、その範囲を明確にすることが重要です。また、借主との契約に「ハウスクリーニング費用の借主負担」を含めることで、この負担を軽減できます。
賃貸相場の調べ方
家を貸すときに気になるのが「いくらで貸せるか」なのではないでしょうか?賃料によっては、貸し出すのではなく、売却したほうがいいと考えられるケースもあるでしょう。ここでは、賃料相場の調べ方を解説します。
類似物件の賃料を調べる
立地や広さ、築年数などが類似している賃貸物件の募集賃料を見れば、ある程度の相場をつかむことができます。ただし、募集賃料と成約賃料は、必ずしもイコールではありません。契約前に値引き交渉があり、家主が了承すれば、賃料は下がる可能性もあります。とはいえ、類似物件は家を貸し出すうえで「ライバル」にもなるため、動向をチェックしておいて損はないでしょう。
不動産ポータルサイトを見る
不動産ポータルサイトでは、物件情報のみならず、賃料相場も公開しています。最寄りの駅名や間取り、建物種別などを絞って家賃相場を調べることも可能です。おおよその賃料の目安を知るには、このような情報を見るのが最も簡単な方法だといえます。
不動産会社に査定を依頼する
賃料は、物件自体の価値とともに周辺の価値や市況を踏まえて設定する必要があります。そのため、物件の適正な賃料を把握する方法として、不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。東急リバブルなら、賃料査定だけでなく売却査定も同時にできるため、家を貸すか売るか悩んでいる方にもおすすめです。
・「マンションを売るか貸すか」に関する記事はこちら
マンションを売るか貸すか決める方法をメリットとデメリットから解説
東急リバブルの「賃貸×売却 無料W査定」はこちらから
家を貸す時の知っておきたいポイント
自分に合った契約形態を選択する
賃貸借契約には「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」があります。自分のニーズに合わせて最適な契約を選ぶことが重要です。たとえば、自分がいずれ戻ってくる可能性があるなら、定期賃貸借契約を選択し、一定期間後に自由に物件を手放せるようにすることも検討しましょう。
信頼できるサポートが充実した不動産会社を選ぶ
賃貸管理は複雑で専門的な知識が必要です。初めて賃貸経営を行う場合は、経験豊富で信頼できる不動産会社を選ぶことが、後のトラブルを防ぐためにも重要となります。不動産会社選びでは、その会社が提供するサポートの内容や顧客レビューをチェックしましょう。
家賃設定はさまざまな要素を加味して検討する
家賃は物件の立地や状態、周辺の市場状況に応じて適切に設定する必要があります。高すぎると入居希望者が見つからず、安すぎると収益性が低下します。競合調査を行い、適正な家賃を設定することが、賃貸経営の成功の鍵を握ります。
借主を選ぶ際には慎重に審査する
適切な借主を選ぶことは、賃貸経営において非常に重要です。家賃の支払遅延や物件の不当な使用を防ぐため、信用情報のチェックや職場情報の確認を徹底しましょう。また、家賃保証会社を利用することで、万が一の家賃滞納にも対応可能です。
入居希望者を募る際には部屋を可能な限り綺麗にする
物件を貸し出す前には、可能な限り清潔で魅力的な状態にしておくことが重要です。ハウスクリーニングの実施や、必要に応じてリフォームや設備の更新を行うことで、入居希望者の関心を引き、早期に契約に結びつけることができます。部屋を常に最良の状態に保つことで、良質な借主からの評価も高まります。
家を貸すときの注意点
家を貸す際には、リスクやデメリットを理解するとともに、次のような点に気をつけましょう。
空室リスクが懸念される
賃貸の最大のリスクの一つが空室期間です。空室期間中は家賃収入を得ることができないため、たとえば分譲マンションの管理費や修繕積立金など家にかかる支出の補填ができないことになるかもしれません。
長期的に入居希望者が見つからない場合は、不動産会社と相談して借主のニーズに合わせた募集条件を設定し直すことが必要です。
管理業務が発生する
賃貸物件を運営する際には、多岐にわたる管理業務が必要となります。具体的には、家賃の集金、入居者のトラブル対応、物件の維持管理などが含まれます。これらの業務は専門的な知識と時間を要するため、多忙な貸主にとっては大きな負担となります。
特に、緊急を要する設備トラブルの対応は迅速かつ適切に行う必要があり、このためにも賃貸管理会社に管理を委託する選択肢が有効です。委託することで、日々の煩わしい管理から解放され、賃貸経営をよりスムーズに行うことが可能となります。
貸主・借主間や入居者同士のトラブルが起こるケースもある
家を貸すことには、貸主と借主、または入居者間でトラブルが生じるリスクも伴います。遅延家賃、物件の損傷、騒音問題などが典型的な例です。これらのトラブルを未然に防ぐためには、契約時にすべての条件を明確にし、契約書に詳細に記載することが重要です。
また、トラブルが発生した場合に備えて、信頼できる不動産会社や法律専門家との連携を密にすることが推奨されます。不動産会社は日常的なトラブル対応に慣れており、適切なアドバイスや介入が可能です。トラブルがエスカレートする前に専門家の助けを求めることで、問題を迅速に解決することができるでしょう。
住宅ローンが残っている場合は金融機関に相談を
住宅ローンが残っている家を貸し出すには、事前に金融機関から承諾を得なければなりません。そもそも住宅ローンとは、自己居住用の不動産に対する融資です。貸し出す行為は契約違反にあたるため、場合によっては投資用ローンへの借り換えを求められます。
所得税・住民税が発生する
家を貸すことで新たに発生する費用があります。それは、税金です。家を貸して得た利益は「不動産所得」にあたります。不動産所得には、所得税と住民税が課されます。不動産所得は、賃料や礼金などの収入から必要経費を差し引いたものです。必要経費は、以下のような費用を指します。
- 借入利息
- 減価償却費
- 固定資産税・都市計画税
- 管理委託費
家を貸すと不動産所得に関する確定申告が必要になる
家を賃貸に出し、家賃収入を得た場合、この収入は税務上「不動産所得」として扱われます。年間で20万円以上の不動産所得がある場合、確定申告が必須となります。これは、給与所得者が会社からの源泉徴収を通じて税務処理されるのとは異なり、家主自身が直接税務署に報告し、税金を納める必要があるためです。
確定申告の手続きは、税務署に直接訪問するか、またはオンラインで便利な「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」を使用して行うことができます。この申告を怠ると、納税義務違反に該当し、結果として無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
したがって、家賃収入が年間20万円を超える場合は、必ず確定申告の期日を守り、適切に申告を完了させることが大切です。このプロセスを通じて、税務上の問題を避け、安心して不動産所得を得ることが可能になります。
・「賃貸用不動産の賃貸時の税金」についてはこちら??
不動産所得の計算方法、必要経費や修繕費に含まれるもの
まとめ
一戸建てやマンションといった家を貸すことは家賃収入を得られるほか、将来再び住むことができるなど売却にはないさまざまなメリットがあります。一方で空室が続くと収入が得られなくなってしまったり、借主との間でトラブルが発生したりといった注意点があるのも確かです。
家を貸すかどうか決める際には、そういったメリットと注意点を踏まえることが重要です。家を貸すかお悩みの方は、まず不動産管理会社に相談することから始めましょう。
この記事のポイント
- 家を貸すメリットは?
賃料収入得られることに加え、インフレ対策にもなり、再び自分たちが住めることが家を貸すメリットです。
詳しくは「家を貸すメリット」をご覧ください。
- 家を貸すときの契約方法は?
「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つがあります。どちらが適しているかは貸し出す期間などによります。
詳しくは「家を貸す方法」をご覧ください。
- 家を貸すときの管理方法は?
「自主管理」「管理委託」「サブリース」の3つに大別されます。
詳しくは「賃貸住宅の管理方法」をご覧ください。
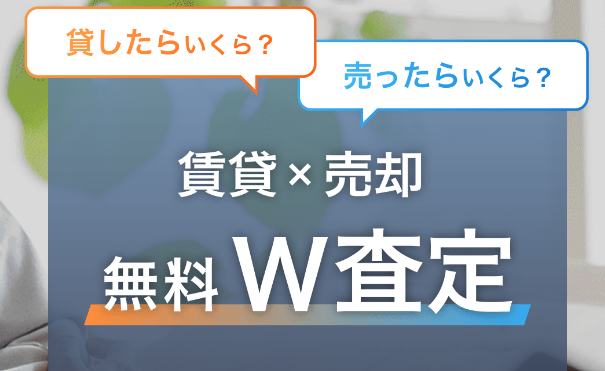
いくらで貸せるの?無料賃料査定
「貸す」も「売る」も相談できる!
賃貸管理プランが充実の東急リバブルにご相談ください。
東急リバブルの賃料査定はこちら

東急リバブルが買主となり、
ご所有不動産を直接購入いたします
リフォームいらず、最短7日間で現金化!
リバブル不動産買取はこちら








