ざっくり要約!
- 隠し部屋は、階段下や屋根裏、地下などに作られることが多いです。
- 隠し部屋は書斎や収納スペース、防災・防犯目的で使用されています。
- 建築確認申請では、隠し部屋の存在を申請する必要があります。
「隠し部屋」は、外から見えないスペースを確保することで、書斎や趣味の部屋、収納として活用できるのが魅力です。しかし、設計する際は、法律上のルールをしっかりと理解しておく必要があります。
本記事では、隠し部屋の活用方法や設置しやすい場所、法的な注意点について詳しく解説します。家の新築やリフォームを考えている方、隠し部屋のある住宅に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
記事サマリー
隠し部屋とは?
隠し部屋とは、一見すると存在が分からないよう工夫された部屋のことを指します。
例えば、本棚や壁面収納の裏側に扉を設け、その先に設置された空間などが典型的な隠し部屋の例です。隠し部屋は、プライバシーの確保や防犯面での利点も持ち合わせています。
隠し部屋の使い道
隠し部屋は、家の中に秘密の空間を設けることで、生活に楽しさや変化を加えられる部屋です。以下で、隠し部屋の主な使い道について説明します。
書斎・テレワークスペース
隠し部屋を個人の書斎やテレワークスペースとして活用することは、有効な使い方です。周りから離れ、集中して作業や読書に取り組むことができます。
特に在宅勤務が増加している現代においては、隠し部屋をワークスペースとして利用することで、仕事と生活のメリハリをつけやすくなります。
・「書斎」に関する記事はこちら
書斎の種類別のメリット・デメリットを解説!快適に利用するためのポイントも紹介
・「書斎」のある物件一覧はこちら
収納
隠し部屋を収納スペースとして利用することで、家全体をすっきりと保つことが可能です。
季節の家電やレジャー用品、普段あまり使用しない物品を収納でき、そのぶん、生活空間を広く使うことができます。
趣味の部屋
趣味に没頭できる空間として隠し部屋を設けるのも一案です。例えば、シアタールームや音楽室として活用することで、家族や友人と仕事の後の時間や休日を楽しむことができます。
防音設備を整えると、他の生活空間への音漏れを気にせず趣味の時間を満喫できます。
防災・防犯目的
隠し部屋を防災や防犯の観点からセーフティルームとして活用することも考えられます。
非常時の避難場所として機能させるため、防犯カメラのモニター設置や非常食の備蓄などが必要です。そうした備えをすることで、家族の安全を確保するための場所となります。
隠し部屋はどんな場所にある?
隠し部屋は、家の中の余剰なスペースを有効活用し、独自のプライベート空間を作り出す手段として注目されています。隠し部屋が設けられる主な場所について、見ていきましょう。
階段下のスペース
階段下のスペースは、デッドスペースになりがちですが、うまく設計することで隠し部屋として有効活用できます。
例えば、階段下の一部に扉を設置し、その奥に小さな書斎や収納スペースを作ることも可能です。天井が低いため、通常の部屋として使うには適していませんが、秘密基地のようなワクワク感を演出できる空間として人気です。
屋根裏・ロフト
屋根裏やロフトは、隠れ家のような雰囲気を演出できる場所です。階段の手前に隠し扉を設置したり、収納型のはしごで上がれるように設計したりすることで、秘密の空間を作り出すことができます。
屋根裏部屋は、傾斜した天井や窓など、独特な空間を生み出せるため、個性的な部屋としてニーズがあります。
地下・床下
地下室は防音性が高く、外部からの視線も遮断できるため、隠れ家として最適な場所です。地下や床下への入り口を工夫することで、家の外からも内からも気付かれにくい空間を作れます。
地下室や床下は、シアタールームや音楽室、セーフティルームなど、様々な用途で活用できます。
隠し部屋は法律的に問題ない?
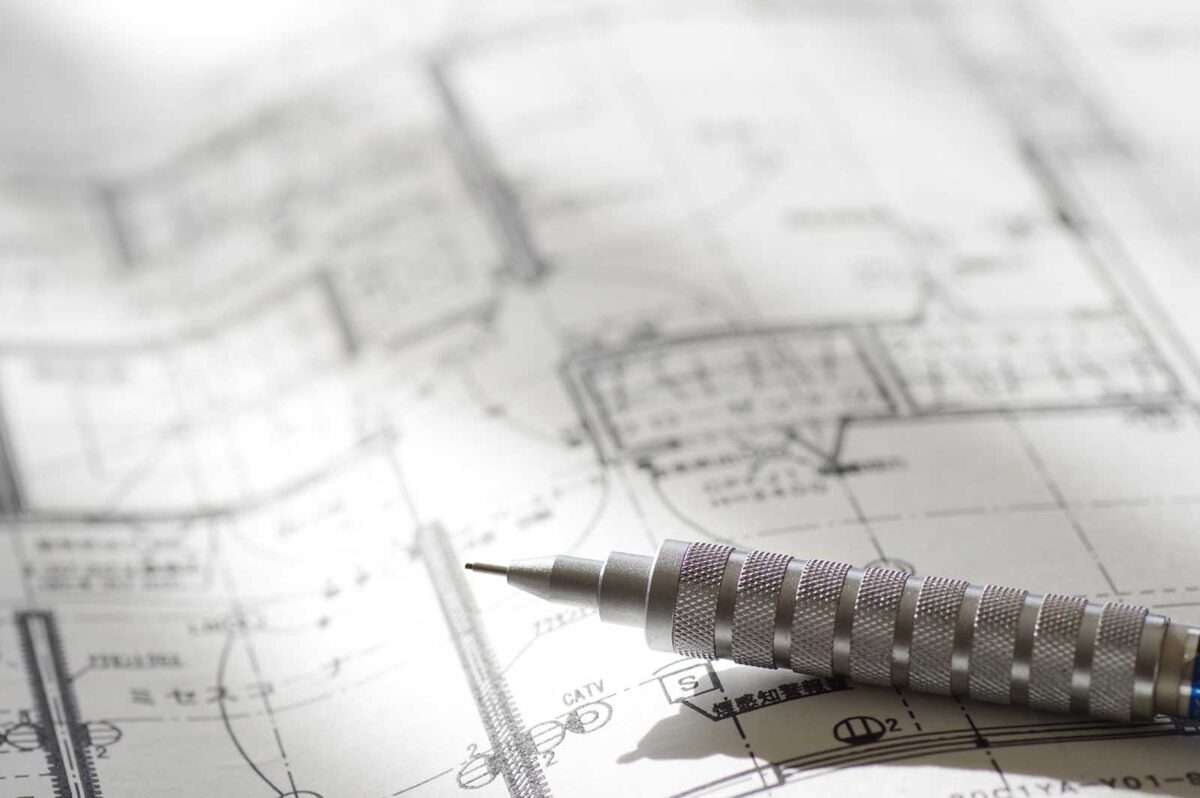
注文住宅に隠し部屋を設けることは、法律上で可能です。ただし、適切な手続きを踏まなければ、問題が生じる可能性があります。詳しく見ていきましょう。
申請しないのはNG
隠し部屋の存在を申請せずに建築すると、建築基準法違反となります。
建築基準法第6条第1項では、建築物の新築や増改築を行う際、確認申請を行うことが義務付けられています。申請では、建物の間取りや床面積を正確に記入しなければなりません。
違反した場合、是正命令や使用禁止命令、さらには罰金などが科されることもあります(建築基準法第9条、第99条)。また、違反建築物であることは、将来的に売却する際に不利になるだけでなく、住宅ローンの審査にも影響を及ぼす可能性があります。
天井高140㎝以下の空間は床面積に含まれない
隠し部屋の天井高さが140㎝以下など一定の要件を満たすと、その部分は床面積に算入されません。建築基準法により、小屋裏物置等として扱われるためです。具体的には、屋根裏や床下を利用した収納スペースなどが該当します。
床面積に算入しない場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 一番高い部分の天井高さが140㎝以下
- 隠し部屋の面積が、その階の床面積の2分の1未満
- 用途が倉庫や物置である
床面積に含まれなくなると、固定資産税などの税金が軽減される可能性があります。
ただし、天井高140㎝以下は大人が立って利用するには不向きであり、収納などの用途に限定されるでしょう。天井高さは「平均」ではなく「一番高い部分」の内法で140㎝以下にする必要があります。
なお、天井高さに関する申請は、一般的に設計士やハウスメーカーが行うため、特別な手続きは必要ありません。
・「床面積」に関する記事はこちら
延べ床面積とは?階段やバルコニーも含まれる?住まいに必要な広さや平均的な面積を解説
隠し部屋がある家を購入するときの注意点
ここでは、隠し部屋がある家を購入する際の主な注意点について解説します。
利用目的を明確にする
物件の購入前に、隠し部屋の利用目的や用途を明確にすることが重要です。例えば、書斎、趣味の部屋、防犯対策のセーフティルームなど、具体的な使用目的を決めておきましょう。
使い道を決めずに購入すると、スペースを有効活用できず、結果的に無駄な空間となる可能性があります。明確な目的を持つことで、購入後の満足度が高まるでしょう。
フレキシブルに利用できるか検討する
将来的に家族構成やライフスタイルが変化した際、隠し部屋を別の用途に転用できるかを考慮しましょう。例えば、当初は書斎として使用していた隠し部屋を、子供部屋や収納スペースとして活用できる設計であれば、長期的に有効活用できます。
フレキシブルに利用できれば、将来的にリフォームを行う手間やコストを抑えられます。
まとめ
隠し部屋は、プライベートな空間を確保したい人や、限られたスペースを有効活用したい人にとって魅力的な選択肢です。書斎やテレワークスペース、収納スペースとして活用することで、暮らしの快適さが向上します。防災や防犯の観点からも、隠し部屋が役立つ場面は多くあります。
ただし、隠し部屋を作る際には、建築基準法のルールを守ることが重要です。不動産会社と相談しながら計画を進めましょう。
この記事のポイント
- 隠し部屋とはどのような部屋ですか?
隠し部屋とは、一見すると存在が分からないよう工夫された部屋のことを指します。
詳しくは「隠し部屋とは?」をご覧ください。
- 隠し部屋はどんな場所に作れますか?
隠し部屋は、家の中の余剰なスペースを有効活用し、独自のプライベート空間を作り出す手段として注目されています。
詳しくは「隠し部屋はどんな場所にある?」をご覧ください。
- 隠し部屋は法律的には問題ないのでしょうか?
注文住宅に隠し部屋を設けることは、法律上で可能です。ただし、適切な手続きを踏まなければ、問題が生じる可能性があります。
詳しくは「隠し部屋は法律的に問題ない?」をご覧ください。
ライターからのワンポイントアドバイス
隠し部屋を作る際は、出入口の形状にもこだわることが大切です。本棚の裏に隠すようなデザインは遊び心がある一方で、開閉がしにくく、実用性に欠ける場合があります。頻繁に出入りする予定の部屋なら、シンプルで使いやすい扉を採用すると快適に過ごせるでしょう。
また、将来的な資産価値や売却時の影響も考慮することが重要です。隠し部屋を魅力的と感じる購入者がいる一方で、使い道が限られるため敬遠される可能性もあります。設計には柔軟性を持たせ、必要に応じて通常の部屋として活用できるようにしておくと安心です。

物件探しや売却がもっと便利に。
無料登録で最新物件情報をお届けいたします。
Myリバブルのサービス詳細はこちら








