ざっくり要約!
- 1坪は平米で表すと約3.3平米で、1辺は約1.82m
- 坪数から平米数に変換したい場合は「坪数÷0.3025」という計算式を使う
住宅や土地などの大きさは「坪」という単位で表されることもあります。「坪」は学校では習わない単位で、馴染みがなく、不動産や建築に携わる人たちが使用している業界用語と言えるかもしれません。
不動産や建築の業界では、なぜ坪という単位が使われるのでしょうか?また、坪を平米に変換するにはどう計算したら良いのでしょうか?
この記事では「坪と平米(平方メートル、㎡)」について解説します。
記事サマリー
坪と平米(平方メートル、㎡)とは?住まいの広さを測る単位まとめ

まずは「坪」や「平米」「畳」など、土地や住宅の広さを表す単位について解説します。
坪
「坪」は、日本で昔から存在する尺貫法の1つの単位です。1坪は、平米で表すと約3.3平米です。正方形にすると1辺が約1.82mになります。尺貫法の1尺(長さの単位)は約30.3cmですので、1辺が6尺の正方形が「坪」という面積です。
また、田んぼや畑の面積は「反(たん)」という単位で表されることがよくありますが、反も坪と関係しています。
まず、30坪を1畝(せ)といい、10畝が1反です。つまり、1反は300坪ということになります。
不動産業界で「坪」は、単価を表す単位として利用されることが多いです。土地単価や建築費単価、マンションの分譲単価、オフィスビルや店舗の賃料単価等を示す「坪いくら」という表現が広く浸透しています。
平米(平方メートル、㎡)
「平米(平方メートル、㎡)」とは、メートル法で面積を表す単位のことです。1辺が1メートルの正方形が、1平米(1平方メートル、1㎡)になります。
メートル法は学校で習う単位であるため、なじみもあり理解しやすい単位です。
不動産の広告も「不動産の表示に関する公正競争規約(以下、公正競争規約)」によりメートル法による表示が指定されています。そのため、チラシやインターネット広告では、分譲マンションや賃貸アパート等の部屋の面積が平米表示となっています。
また、メートル法は広く浸透していることから、近年は田んぼや山林の面積もメートル法で表示されることが多いです。
田んぼや山林の価格は、「10a(アール)」当たりの単価で示されることがよくあります。1aは100平米ですので、10aは1,000平米ということになります。
1,000平米は坪に換算すると302.5坪であり、約1反(1反は300坪)ということです。
田んぼや山林の価格が10a当たりの単価で表記されることが多いのは、「1反いくら」の尺貫法の文化を引き継いでいるためだと思われます。
畳
「畳(じょう)」とは、畳1枚分の面積を表す単位です。畳は地域によって面積が異なりますが、公正競争規約では、畳1枚当たりの広さは「1.62平米」以上とするというルールを設けています。
一方で、全国で使用されている主な畳の面積を示すと以下の通りです。
| 畳の種類 | 面積 |
|---|---|
| 中京間 | 約1.65平米 |
| 京間 | 約1.82平米 |
| 江戸間 | 約1.54平米 |
| 団地間 | 約1.44平米 |
公正競争規約で定められている「1.62平米」は、中京間の約1.65平米に近い数値が採用されています。
中京間は主に東海地方で使われている畳です。「三六間(さんろくま)」とも呼ばれており、幅が3尺、長さが6尺となっています。
1尺は約30.3cm、3尺は約90.9cm、6尺は約1.82mとなります。3尺に6尺を乗じると、約1.65平米となります。1.65平米を2倍すると約3.3平米となるため、中京間の2畳分が1坪ということです。つまり、1坪=2畳、1畳=0.5坪という関係になります。ただし、前述の通り畳は種類によって面積が異なりますので、一般的に1坪は“約”2畳と表現されることが多いです。
また、不動産や建築業界で未だに坪表記がなされる理由は、畳によるところが大きいといえます。
日本家屋では、畳のサイズを基本として柱を設置し、部屋の大きさを決めていくという考え方がありました。畳を起点にして家の大きさを決めていたことから、2畳で正方形となる1坪という単位が便利であったものと思われます。
畳のサイズを起点とする家づくりは、現在でも多くの部分に残されています。
例えば、リビング等の大きな窓の幅は一般的に約90cmであり、これは畳の短辺に相当します。
引き違いの窓が2枚あれば、その幅は約180 cmであり、畳の長辺とほぼ同じです。
約180 cmというサイズは「1間(けん)」であり、6尺に相当します。中京間は長辺が6尺、短辺が3尺でした。つまり、「1間×0.5間」が畳であり、「1間×1間」が坪ということになります。
畳の長辺と短辺は、日本家屋の部材の幅を決める1つのモジュール(基準寸法)です。日本の住宅には畳をモジュールとした規格品が広く浸透していることから、不動産や建築業界で未だに坪表記が多く用いられていると考えられます。
坪数、平米数(平方メートル、㎡)、畳数へ変換する計算方法

続いて、坪数から平米数など、単位を変換する際の計算方法について解説します。
| 変換する単位 | 計算式 |
| 坪数から平米数へ | 平米数 = 坪数 ÷ 0.3025 |
| 平米数から坪数へ | 坪数 = 平米数 × 0.3025 |
| 畳数から平米数へ | 平米数 = 畳数 × 1.62 |
| 平米数から畳数 | 畳数 = 平米数 ÷ 1.62 |
坪数から平米数へ変換する計算方法
坪数から平米数への変換する際は、次のように計算します。
平米数 = 坪数 ÷ 0.3025
30坪を例に計算すると、以下になります。
30坪 ÷ 0.3025 ≒ 99.2平米
平米数から坪数へ変換する計算方法
平米数から坪数の変換は、以下の計算式を用います。
坪数 = 平米数 × 0.3025
60平米を例に計算すると、以下になります。
60平米 × 0.3025 = 18.15坪
畳数から平米数へ変換する計算方法
畳数から平米数の変換は、以下の計算式を用います。ここでは、畳の広さを公正競争規約で定められている「1.62平米」を採用します。
平米数 = 畳数 × 1.62
40畳を例に計算すると、以下になります。
40畳 × 1.62 = 64.8平米
平米数から畳数へ変換する計算方法
平米数から畳数の変換は、以下の計算式を用います。
畳数 = 平米数 ÷ 1.62
60平米を例に計算すると、以下になります。
60平米 ÷ 1.62 ≒ 37.03畳
【早見表】平米数・坪数・畳数
坪数に対するおおよその平米数および畳数は、以下のとおりです。
| 坪数 | 平米数(㎡) | 畳数(1畳1.62㎡) |
| 1坪 | 約3.3平米 | 約2畳 |
| 10坪 | 約33.1平米 | 約20畳 |
| 20坪 | 約66.1平米 | 約40畳 |
| 30坪 | 約99.2平米 | 約60畳 |
| 40坪 | 約132.2平米 | 約80畳 |
| 50坪 | 約165.3平米 | 約100畳 |
| 100坪 | 約330.6平米 | 約200畳 |
坪数と平米数(平方メートル、㎡)をもとにした世帯人数別・住まいの広さ

国土交通省では、「住生活基本計画」において豊かな住生活の実現の前提として多様
なライフスタイルに対応するために必要と考えられる、住宅の面積(誘導居住面積水準)の目安を公表しています。
誘導居住面積水準には「一般型誘導居住面積水準」と「都市居住型誘導居住面積水準」の2種類があります。
一般型誘導居住面積水準とは、都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定した面積のことです。
一方、都市居住型誘導居住面積水準とは、都市の中心及びその周辺における共同住宅居住を想定した面積になります。
また、健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積として「最低居住面積水準」も公表しています。
2021年3月19日に閣議決定された住生活基本計画によると、一般型誘導居住面積水準と都市居住型誘導居住面積、最低居住面積水準の面積は下表の通りです。
| 区分 | 世帯人数 | 面積 |
|---|---|---|
| 一般型誘導居住面積水準 | 単身者 | 55平米 |
| 2人以上の世帯 | 25平米×世帯人数+25平米 | |
| 都市居住型誘導居住面積水準 | 単身者 | 40平米 |
| 2人以上の世帯 | 20平米×世帯人数+15平米 | |
| 最低居住面積水準 | 単身者 | 25平米 |
| 2人以上の世帯 | 10平米×世帯人数+10平米 |
一般型誘導居住面積水準と都市居住型誘導居住面積による面積は、感覚的にはいずれもゆったりとした印象のある広めの面積です。
若干、広い面積ではあるものの、ここでは主に都市居住型誘導居住面積水準を用いながら世帯人数別・住まいの広さの目安について解説します。
2人暮らしの場合(夫婦・カップルなど)
都市居住型誘導居住面積水準では、2人暮らしの適正面積は「20平米×世帯人数+15平米」です。
つまり、55平米(=20平米×2人+15平米)が適切な広さといえます。
55平米は、坪に換算すると約17坪弱、畳に換算すると約34畳です。
公正競争規約ではDKまたはLDKの最低必要な広さの目安も定めています。
DKとは、ダイニング・キッチン、LDKはリビング・ダイニング・キッチンの略です。
公正競争規約によるDKとLDKの目安は以下のように定められています。
| 居室数 | DK | LDK |
|---|---|---|
| 1部屋 | 4.5畳(7.29平米) | 8畳(12.96平米) |
| 2部屋以上 | 6畳(9.72平米)以上 | 10畳(16.2平米)以上 |
近年は、リビングのないDKの間取りは人気がないため、築浅物件では少ないです。
比較的新しい物件であれば、LDKの物件が多いものと思われます。
55平米となると、「広めの1LDK」もしくは「2LDK」の間取りが一般的です。
2人暮らしであれば、十分にゆとりのある生活ができる広さといえます。
3人暮らしの場合(親子・ルームシェアなど)
住生活基本計画では、世帯人数は3歳未満は 0.25 人、3歳以上6歳未満は 0.5 人、6歳以上 10 歳未満は 0.75 人として算定するものとしています。
都市居住型誘導居住面積水準によって、親子で年齢別の適正な広さを計算すると下表の通りです(計算式は「20平米×世帯人数+15平米」を用います)。
| 子どもの年齢 | 計算式 | 面積 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 20平米×2.25人+15平米 | 60平米(約18坪) |
| 3歳以上6歳未満 | 20平米×2.5人+15平米 | 65平米(約20坪) |
| 6歳以上 10 歳未満 | 20平米×2.75人+15平米 | 70平米(約21坪) |
| 10歳以上 | 20平米×3人+15平米 | 75平米(約23坪) |
ルームシェアする方は10歳以上と考えられるため、面積は75平米(=20平米×3人+15平米)が適切な水準ということになります。
4人暮らし以上の場合(親子・三世代同居など)
住生活基本計画では、4人を超える場合は、求められた面積から5%を控除するとしています。
都市居住型誘導居住面積水準で4人と5人の適正面積を計算すると、下表の通りです。
【都市居住型誘導居住面積水準】
| 世帯人数 | 計算式 | 面積 |
|---|---|---|
| 4人 | (20平米×4人+15平米)✕95% | 90.25平米(約27坪) |
| 5人 | (20平米×5人+15平米)✕95% | 109.25平米(約33坪) |
世帯人数が4~5人となる場合、戸建て住宅を選択するケースも多いと思われます。
戸建て住宅の水準を示す一般型誘導居住面積水準で適正面積を計算すると、下表の通りです。
【一般型誘導居住面積水準】
| 世帯人数 | 計算式 | 面積 |
|---|---|---|
| 4人 | (25平米×4人+25平米)✕95% | 118.75平米(約36坪) |
| 5人 | (25平米×5人+25平米)✕95% | 142.50平米(約43坪) |
首都圏中古戸建ての平均面積
参考までに公益財団法人東日本不動産流通機構の「首都圏不動産流通市場の動向(2023年)」によると、2023年に首都圏で取引された中古戸建ての平均面積は以下のようになっています。
| 土地面積 | 143.79平米(約43坪) |
| 建物面積 | 103.96平米(約31坪) |
出典:東日本不動産流通機構
一般型誘導居住面積水準で計算した4人の適正面積は118.75平米のところ、首都圏の中古戸建ての平均面積は103.96平米でした。
首都圏では、一般型誘導居住面積水準よりも一回り小さい面積の戸建て住宅が市場で多く流通していることになります。
まとめ
住宅や土地の広さを表す単位は複数あるためわかりにくいですが、坪数から平米数へ変換したいときは「0.3025」を乗じたり除したりすることで計算できます。
一方、畳数から平米数に変換したい場合は、畳数に「1.62」を乗じることで導き出せます。ただし、畳の大きさによって多少の差が生じることもあるためご注意ください。
この記事のポイント
- 坪から平米に変換したい場合はどうすればいい?
坪数から平米数へ変換する際は、次のように計算します。
平米数 = 坪数 ÷ 0.3025詳しくは「坪から平米への変換式【計算例あり】」をご覧ください。
- 坪と平米をもとにした世帯人数別・住まいの広さの目安は?
例えば2人暮らしの場合、適正面積は「20平米×世帯人数+15平米」です。つまり、55平米(=20平米×2人+15平米)が適切な広さといえます。
55平米は、坪数に換算すると17坪弱、畳に換算すると約34畳です。
詳しくは「坪と平米をもとにした世帯人数別・住まいの広さ」をご覧ください。
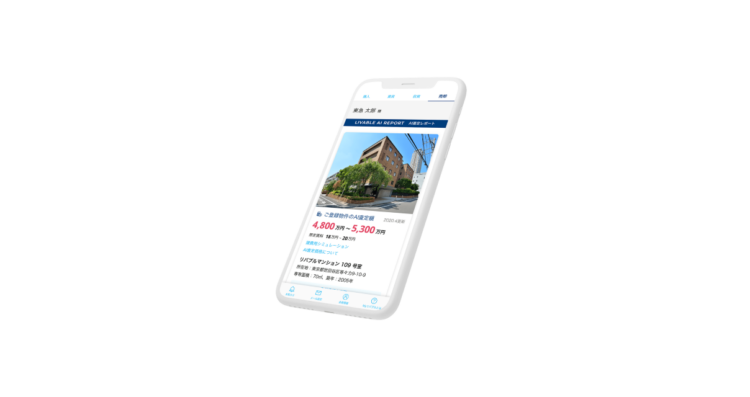
査定は手間がかかりそう。そんな人にはAI査定!
ご所有不動産(マンション・一戸建て・土地)を登録するだけでAIが査定価格を瞬時に算出いたします
スピードAI査定をしてみる








