ざっくり要約!
- 親から相続するマンションの遺産分割協議では相続人全員が合意する必要がある
- 親が所有していたマンションを子供が相続せずに放棄することも可能
親のマンションを兄弟で相続することになったら、何から始めたらよいのでしょうか。相続はいつ発生するか分かりませんし、相続対策は万全だという人の方が少数派でしょう。
今回は親のマンションを兄弟で相続することになった方向けに、相続手続きの基本的な流れや法定相続分による分割、相続登記に必要な書類までわかりやすく解説します。
また遺産分割協議に関する注意点や、忘れてはいけない手続きについても触れますので、ぜひ最後までお付き合いください。
記事サマリー
子供がマンション相続する場合の基本的な流れ

まず、相続が発生してから相続税を申告・納付するまでの手順を把握するために、おおまかな流れを5つのステップで解説します。
1.遺言書の有無と内容の確認
まず、被相続人が遺言書を残しているか確認します。
遺言書を作成していれば、基本的には遺言書の内容にしたがって遺産分割をおこないます。
ただし相続人全員が同意すれば、かならずしも遺言書どおりに相続する必要はありません。
もし民法で定められた最低限相続できる割合(遺留分)を侵害する場合は、遺産分割協議で変更について話し合いましょう。
遺言書にはその場で開封できる「公正証書遺言」と、改ざんを防ぐために家庭裁判所で手続きが必要な「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」があります。
遺言書の種類によって手続きが異なるため、開封する際は注意が必要です。
遺言書がない場合は相続人で遺産分割協議をおこない、遺産分割協議により分割の割合を決めるか、法定相続分(民法で定められた割合)に基づいて分割します。
2.相続人と遺産の調査
次に、相続人と遺産の調査をおこないます。
配偶者は常に相続人になり、被相続人に子供がいる場合は、被相続人の父母は相続人になりません。第1順位の相続人がいない場合のみ、次の順位である人が相続人になります。
| 相続人の範囲 | 被相続人との関係 |
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子供(子供が死亡している場合は孫) |
| 第2順位 | 父母(父母が死亡している場合は祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟(兄弟が死亡しているときは、その子ども) |
相続人を決定する場合は、被相続人の戸籍謄本を確認する必要があります。
たとえば認知した子ども(婚外子・非嫡子)がいれば、子どもと同じように相続人になるため、慎重に調査するようにしましょう。
遺産は預貯金や不動産、株式などが対象になり、借金など負の遺産も対象になります。
たとえばマイナスの遺産が多い場合、遺産をすべて放棄することも可能です。遺産を分割する際は、よく調査したうえで決定しましょう。
3.遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産をどのように分割するか相続人全員で話し合うことをいいます。
相続全員の同意があれば、遺言書と異なる割合で相続することができます。しかし相続人が1人でも欠ければ、遺産分割協議は成立しません。
遺産をどのように分割するか決定したら、その内容を書面にまとめます。相続人全員の署名と実印を押印したら、遺産分割協議書は完成です。
遺産分割協議書の作成が難しい場合は、司法書士へ依頼しましょう。
4.相続登記
遺産分割協議が整ったら、不動産については相続登記をおこないます。
相続登記とは、不動産の所有者を故人から相続人に変更する登記のことです。
相続人が登記簿上の所有者になれば、不動産を売却できるようになります。
なお2024年4月1日から相続登記は義務化されたため、なるべく早めに相続について協議し、相続登記を終えるようにしましょう。もし正当な理由がなく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
相続登記は個人でも申請できますが、法定相続人の特定や戸籍の証明書などを揃える必要があります。難しい場合は、司法書士への依頼を検討しましょう。
出典:登記申請手続きのご案内(相続登記①遺産分割協議編)|法務省民事局
5.相続税の申告と納付
相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた場合に発生します。
基礎控除は以下の計算式で求めます。
遺産に係る基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
たとえば兄弟3人で相続する場合は、基礎控除額は4,800万円です。
相続財産が4,800万円以下であれば相続税は発生せず、申告も不要です。
もし相続税が発生する場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に税務署に相続税について申告し、相続税を納付しなければなりません。相続税が発生するか否かについては、早めに確認しておきましょう。
ちなみに兄弟の中に未成年がいる場合は未成年者の税額控除を利用でき、一定の条件を満たす場合は、未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円が控除できます。
・「遺産相続の手続きの流れ」に関する記事はこちら
遺産相続の手続きの流れは?相続人や相続割合、税金についても解説
子供がマンション相続する前に知っておきたい法定相続の割合

もし親の所有していたマンションを、子供である自分が相続する予定であれば、法定相続分について理解しておきましょう。
法定相続分とは、相続人が遺産分割について協議した結果、合意に至らなかったときに採用する遺産の割合(持分)のことです。
民法によって、子供や父母(直系尊属)、兄弟姉妹が2人以上いるときは原則均等に分けるよう定められています。
配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の相続人が誰になるかで法定相続分は変動します。たとえば第1順位の子供と遺産分割する場合は、配偶者の法定相続分は1/2です。
もし子供がいない場合は、第2順位の被相続人の父母と遺産分割することになり、そのときの法定相続分は2/3になります。
そして第1・第2順位の人がいなければ、配偶者は第3順位の被相続人の兄弟姉妹と遺産分割することになり、法定相続分は3/4です。
しかしあくまでも基準であり、必ずしも法定相続分で分割しなければならない訳ではありません。
| 法定相続人 | 配偶者の法定相続分 | 配偶者以外の法定相続分 |
| 配偶者・子ども | 1/2 | 1/2(子どもで均等に分割) |
| 配偶者・父母(直系尊属) | 2/3 | 1/3(直系尊属で均等に分割) |
| 配偶者・兄弟 | 3/4 | 1/4(兄弟で均等に分割) |
第1順位:被相続人の子ども(子どもが死亡している場合は、その子供)
第2順位:被相続人の父母(父母が死亡しているときは祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟
ここでは参考例として、法定相続分で分割する2つのケースについて解説します。
配偶者と子供がいる場合
配偶者と2人の子供が相続人の場合、法定相続分は以下の通りです。
配偶者は1/2で、残りの1/2を子供2人で均等に分割するため、子供はそれぞれ1/4ずつになります。
子供が3人の場合でも、配偶者の1/2で変わりません。子供は1/2を3人で分割するため、それぞれ1/6ずつになります。
| 法定相続人 | 配偶者の法定相続分 | 配偶者以外の法定相続分 |
| 配偶者・子ども | 1/2 | 1/2(子どもで均等に分割) |
子供だけで分ける場合
配偶者がすでに亡くなっている場合で、子供2人で遺産を分割する場合は、それぞれ1/2になります。
子供が3人であれば、1/3ずつ分割することになります。子供がいる場合は、第2順位や第3順位の人には、法定相続分はありません。
子供がマンション相続したら相続登記が必要【手続きと費用】

以前は不動産を相続してもすぐに登記しないケースがありましたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されたため、所有権取得を知ったときから3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由がなく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。相続したら後回しにせず、なるべく早めに登記するようにしてください。
ここでは、相続登記に必要な書類や費用について解説します。
不動産の相続登記の手続きと必要な書類
マンションの相続登記をする場合は以下の書類が必要になり、法務局の窓口へ直接提出するか、郵送で送ります。
相続登記の申請手続き自体は個人でも可能ですが、用意しなければならない書類が多いため、司法書士へ依頼した方がスムーズでしょう。
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
- 不動産を相続する人の住民票
- 相続対象の固定資産税明細書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(作成した場合)
出典:登記申請手続きのご案内(相続登記①遺産分割協議編)|法務省民事局
相続登記で発生するおもな費用
相続登記で発生する費用は、おもに以下の通りです。
登録免許税
登録免許税とは、登記する際にかかる税金です。
下記の計算式で求めることができます。
・登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%
司法書士への報酬
相続登記を司法書士へ依頼した場合、報酬として10~20万円ほどかかります。
必要書類の取得費
戸籍や住民票、印鑑証明書などの取得費です。
それぞれは数百円程度ですが、すべてを用意すると数千円程度かかります。
マンション相続で話し合う際の注意点【子供たちの遺産分割協議】

被相続人の遺言書がない場合、法定相続分で分割するのが一般的ですが、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合(持分)で相続することも可能です。
親から相続することになったマンションについて遺産分割協議をする場合は、いくつか注意すべきポイントがあります。ここでは、代表的な注意点を3つ紹介します。
相続人全員の合意を得る
遺産分割協議は、相続人全員が合意する必要があります。
1人でも欠けてしまった場合や、1人でも同意しない人がいれば遺産分割協議は無効です。
ただし全員が一堂に会する必要はなく、電話やオンラインでも構いません。また書面を持ち回りして、遺産分割について協議する方法もあります。
もし一部の人の合意が得られない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることを検討しましょう。
未成年がいる場合は特別代理人を立てる
未成年者(17歳以下)は法律上「制限行為能力者」であり、遺産分割協議に単独で参加することはできません。
未成年者の法定代理人は親権者がなるのが一般的ですが、親権者もまた相続人であることも少なくありません。
未成年者と共同相続人である親権者が法定代理人になると、「利益相反」の関係になってしまいます。つまり親権者が法定代理人になることで、未成年者に不利に働く可能性は否めません。
このような場合は家庭裁判所に申し立てをし、未成年者の特別代理人を選任してもらうことになります。
遺産分割に期限はないが相続税申告の期限がある
遺産分割協議について、法律上の期限はありません。しかし相続税が発生する場合は、被相続人が亡くなったことを知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に、相続税について申告する必要があります。
申告期限までに申告をしない場合、本来納付する税金とは別に、加算税や延滞税がかかることがあるので注意しましょう。
マンション相続を子供が放棄することも可能

親が所有していたマンションを相続せず、放棄することも可能です。
親の借金などの債務を放棄したいときは、ほかの財産をすべて放棄することで債務についても放棄できます。
これを「相続放棄」といい、ほかにも権利だけでなく債務も受け継ぐ「単純承認」や、限定して相続する「限定承認」があり、相続人はいずれかを選択できます。
どの相続の仕方がよいのか検討するためにも、親の遺産を正しく把握することが重要です。なお放棄する(相続放棄もしくは限定承認)場合は、相続を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
ただし、マンションを相続する者がいない場合、相続放棄したとしても管理義務は残ります。その場合は家庭裁判所に申し立てて、相続財産管理人を選任してもらいましょう。
選任後は、管理費等の支払いは発生しません。ただちに管理費や修繕費用の支払いが免除されるわけではありませんので注意してください。
単純承認
マンションなどの所有権だけでなく、借金を返済する債務もすべて受け継ぐ
相続放棄
マンションなどの所有権だけでなく、借金などの債務もすべて放棄する
限定承認
被相続人の債務について不明なため、相続によって得た財産を限度として、被相続人の債務も受け継ぐ
出典:相続の放棄の申述|裁判所
マンション相続する子供が注意すべきポイント

親のマンションを子供が相続する場合、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。ここでは、特に大切な3つのポイントを紹介します。
住宅ローンが残っていないか確認
まず住宅ローンが残っていないかチェックし、残っている場合は団体信用生命保険(団信)に加入しているのか確認しましょう。
団信に加入していれば契約者が亡くなったことで完済になりますが、加入していない場合は相続人が残りのローンを支払うことになります。
公共料金の名義変更または解約・管理組合への連絡
親のマンションを相続したら、公共料金の名義変更もしくは解約をしましょう。万が一未納分があれば、相続人である自分が支払うことになります。
またマンションの所有者は、原則管理組合の組合人になります。所有者が変更になった旨を連絡し、区分所有者変更手続きをおこないます。
管理費や修繕積立金の口座振替などの手続きも必要で、未払いがあれば相続人が支払いうことになります。
空き家のまま放置せず売却か賃貸を検討
マンションは換気をしないとカビが生えやすくなり、設備を使用しない期間が長すぎると、劣化を早めることになります。
相続したマンションは空き家のまま放置せず、なるべく早く賃貸物件として貸し出すか、築年数が古くなる前に売却を検討しましょう。
この記事のポイント
- マンション相続における法定相続分とは?
法定相続分とは、相続人が遺産分割について協議した結果、合意に至らなかったときに採用する遺産の割合(持分)のことです。
民法によって、子供や父母(直系尊属)、兄弟姉妹が2人以上いるときは原則均等に分けるよう定められています。詳しくは「子供がマンション相続する前に知っておきたい法定相続の割合」をご覧ください。
- マンション相続で話し合う際の注意点は?
マンション相続などの遺産分割協議は、相続人全員が合意する必要があります。1人でも欠けてしまった場合や、1人でも同意しない人がいれば遺産分割協議は無効です。
ただし全員が一堂に会する必要はなく、電話やオンラインでも構いません。また書面を持ち回りして、遺産分割について協議する方法もあります。詳しくは「マンション相続で話し合う際の注意点【子供たちの遺産分割協議】」をご覧ください。
ライターからのワンポイントアドバイス
相続が発生すると、遺産分割協議や相続登記などすべきことたくさんあり、何から進めたらよいのかわからないと悩んでいる方は多いかもしれません。まず相続人は何人なのか、遺産はどれくらいあるのか調査し、相続税が発生するのか確認することから始めましょう。
遺産分割に期限はありませんが、相続登記は3年以内に行わなければなりません。マンションを売却する予定であれば、空き家の期間を短くするためにも、早めに遺産分割協議をおこない、売却する準備を進めましょう。
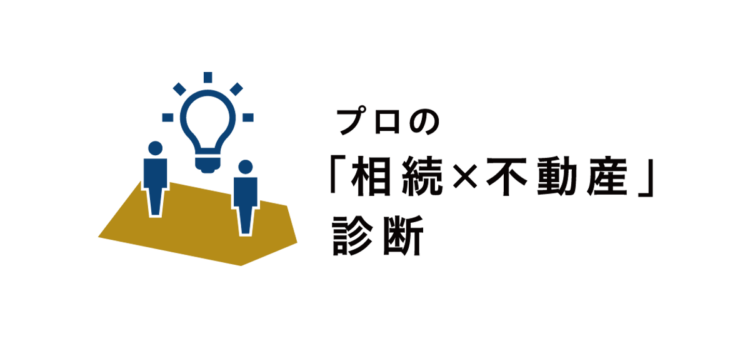
東急リバブルの相続サポート
不動産相続のことなら、東急リバブルの相続サポートにお任せください。
不動産のプロと相続のプロがトータルサポートいたします。
プロの「相続×不動産」診断はこちら








