ざっくり要約!
- 兄弟でマンション相続する際の遺産分割協議では相続人全員で話し合うことが必要
- 遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所に調停または審判の申立を行うことも可能
相続で揉める原因は、極論すると遺産の中に不動産のような分けにくい財産が含まれていることです。
相続財産の中にマンションがある場合、マンションをどう分けるかが悩みどころです。
平等性を重視するなら売ってから現金を分ける方法もありますし、継続利用を重視するなら兄弟(姉妹)の一方に偏らせて分ける方法が考えられます。
何を重視するかで分け方は異なりますので、分割方法よりも先に兄弟で重視したいことを決めることが望ましいです。
この記事では、「兄弟のマンション相続」をテーマに解説します。
記事サマリー
マンション相続を兄弟でするときの手続き

親が亡くなった場合は、遺産を子どもたちで分けることになります。
最初に、マンションを兄弟で相続する場合の流れや手続きを解説します。
1.遺言書の確認または遺産分割協議
法定相続分以外の割合で遺産を分けるには、遺言による分割と遺産分割協議による分割の2種類があります。
遺言とは、遺言者の生前の最終意思を尊重し、その意思の実現を死後に図る制度のことです。
遺言では、被相続人(死亡した人)が遺産の分割割合を決めることができます。
それに対して、遺産分割協議とは被相続人の死後に相続人が分割方法を決める話し合いのことです。
遺言も遺産分割協議も共通点は遺産を分ける方法ですが、相違点は誰が遺産の分け方を決めるかという点です。
遺産の分け方を被相続人が決める場合は遺言、相続人が決める場合は遺産分割協議ということになります。
遺言が存在する場合には、遺言に従って遺産を分けるのが原則です。
そのため、相続が発生した場合には、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。
一方で、遺言書がない場合や、もしくは遺言書があっても遺言書とは異なる割合で分割したい場合には、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要です。
例えば、遺言書と異なる割合で分けたいと思っても、1人でも反対者がいれば遺産分割協議が成立しないため、遺言書に従って分けざるを得ないことになります。
遺言書が持つ力は強力であることから、最初に遺言書の有無を確認することが重要となるのです。
2.相続登記
相続登記とは、相続を原因とした名義変更のことです。
相続登記は、2024年4月1日より義務化されています。
相続登記の期限は、「相続で取得したことを知った日から3年以内」です。
相続登記に必要な書類は分割方法によって異なり、下表のようになります。
| 分割方法 | 必要書類 |
| 遺言による分割 | ・遺言書 ・遺言者の死亡事項の記載のある除籍謄本 ・相続人または受遺者の現在の戸籍謄本 ・遺言により相続または受贈する相続人 ・受贈者の現在の住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
| 遺産分割協議による分割 | ・遺産分割協議書 ・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続したすべての戸籍謄本など ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ・遺産分割により相続する相続人の現在の住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
| 法定相続による分割 | ・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続したすべての戸籍謄本など ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・相続人全員の現在の戸籍謄本 ・被相続人の除住民票または戸籍の附票 ・固定資産評価証明書 |
法定相続による分割とは、法定相続割合のまま共有で物件を持つ分割方法のことです。
法定相続割合とは、民法で定められた相続人が財産を相続できる割合のことを指します。
遺言書がなく、かつ遺産分割協議もまとまらない場合には、法定相続による分割が選択肢となります。
3.必要に応じて相続税の申告と納付
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
必要があれば、期限までに相続税の申告と納付をする必要があります。
相続税は、被相続人の正味遺産額が基礎控除額を超える場合に課税される税金です。
正味遺産額とは、マンション等のプラスの財産から借金等のマイナスの財産を控除するといった所定の手続きによって求めた財産額になります。
課税遺産総額 = 正味遺産額 ― 基礎控除額
基礎控除額の計算式は、以下の通りです。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円(=3,000万円+(600万円×3))ですので、正味遺産額が4,800万円超であれば相続税の申告が必要となります。
逆に正味遺産額が基礎控除額を下回っている場合には、相続税の申告は不要です。
マンション相続を兄弟でおこなうときの遺産分割方法

遺産の分割方法は必ずしも法定相続分で分けるとは限らず、現実的には法定相続分以外の割合で分割されることが多いです。
遺産の分け方には、大きく分けて4種類があります。
この章では、遺産分割方法について解説します。
現物分割
現物分割とは、被相続人の不動産や現金、車、貴金属などの財産を現物そのままの形で相続人の間で分ける分割方法です。
現物分割では、それぞれの資産を単独所有とするように分けることが一般的となっています。
現物分割のメリットは、単独所有となるため、その後の財産の活用や売却が行いやすくなるという点です。
デメリットは、法定相続割合で公平に分けにくい点が挙げられます。
代償分割
代償分割とは、相続人のうち、財産を多く相続した人が他の相続人に代償金を支払うことで公平性の均衡を図る分割方法のことです。
代償分割のメリットは、特定の人が多くの不動産を引き継ぐことができるという点が挙げられます。
代償分割は、個人で商売を行っている家で用いられることが多いです。
後継者が店舗の土地等を相続でき、家業を無事に継続できるようになります。
デメリットは、財産を引き継いだ人が多くの代償金を払うため、引き継いだ人の経済的な負担が重いという点です。
換価分割
換価分割とは、不動産など売却し、その後に現金を分ける分割方法のことです。
換価分割のメリットは、財産を公平に分けることができるという点が挙げられます。
デメリットは、売却の手間がかかるという点です。
換価分割を行う際は、マンションを法定相続による分割によって共有することが合理的といえます。
共有分割
共有分割とは、遺産を主に法定相続割合のまま共有する分割方法のことです。
遺産分割が成立しない場合には、共有分割によって物件を持ち続けることがよくあります。
共有分割のメリットは、遺産分割の手間も不要であり、法定相続分で公平に財産を分けられるという点です。
デメリットは、共有物件は売却するときに共有者全員の同意が必要となるため、単独所有よりも売却しにくくなる点が挙げられます。
兄弟でマンション相続する際の遺産分割協議の注意点

遺産分割協議をおこなう際はいくつか注意点が存在します。
この章では、遺産分割協議による分割を行う際の注意点を解説します。
相続人全員で話し合う
遺産分割協議は、相続人全員で話し合うことが必要となります。
理由としては、遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要となるからです。
例えば、被相続人が離婚しており、被相続人の前妻との間に子がいる場合は、その子も相続人となります。
遺産分割協議を行うには、前妻の子も呼び寄せることが必要です。
なお、遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所に調停または審判の申立を行うこともできます。
遺産分割協議書は必ず作成する
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容をまとめた書面のことです。
遺産分割協議書は、相続登記等の必要書類となるため、必ず作成する必要があります。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。
未成年がいる場合は代理人が必要
未成年者は遺産分割協議に参加できないため、代理人が必要です。
代理人は、基本的には父母等の親権者となりますが、親権者自身が未成年者とともに共同相続人の一人である場合、代理人と子が利益相反になる可能性があります。
そのため、親権者が共同相続人の一人である場合には、家庭裁判所に特別代理人と呼ばれる代理人を申立て、特別代理人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。
兄弟でマンション相続する際に起こりやすいトラブル

兄弟でマンションを相続する際に発生しやすいトラブルを紹介します。
親と同居していたマンションの売却を要求される
遺産の構成が1つのマンションと少額の現金だけのような場合、トラブルが起きやすいです。
特に、1人の相続人が親と同居しており、マンションを売れないようなケースだと分割で揉めやすくなります。
例えば、遺産がマンションの2,500万円と現金500万円という場合があるとします。
兄がマンションに住んでおり、弟が他の場所で住んでいる場合には、兄がマンション、弟が現金を引き継ぐことが多いです。
このケースでは、兄が2,500万円、弟が500万円の遺産を引き継ぐため、両者に大きな不平等が生じます。
弟が平等にこだわる場合には、兄がマンションの売却を迫られるというトラブルもあります。
解決策としては、兄が代償金を払うか、もしくは家庭裁判所に調停または審判を申立て遺産分割の決着を付けることが考えられます。
共有分割した後に共有者が死亡した場合の対処でもめる
共有分割では、放置しておくとそのうち共有者の一人が死亡し、さらに共有者が増えてしまうトラブルが発生します。
実際、山林等の資産価値のない不動産では、何代も相続が繰り返されて共有者が100人以上となっている物件も存在します。
共有物件の売却には共有者全員の同意が必要であるため、多人数共有物件になってしまうと売却の合意を取れず、現実的に売却できなくなることも多いです。
対策としては、共有分割は極力選択しない、もしくは共有分割を選択しても共有者が少ないうちに早めに売ってしまうことが考えられます。
この記事のポイント
- マンション相続を兄弟でおこなうときの遺産分割方法は?
マンション相続を兄弟でおこなうときの遺産分割方法としては、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があります。
詳しくは「マンション相続を兄弟でおこなうときの遺産分割方法」をご覧ください。
- 兄弟でマンション相続する際の遺産分割協議の注意点は?
遺産分割協議の注意点としては、相続人全員で話し合うこと、遺産分割協議書を必ず作成することが挙げられます。
詳しくは「兄弟でマンション相続する際の遺産分割協議の注意点」をご覧ください。
ライターからのワンポイントアドバイス
マンションのような不動産は、兄弟間で平等に分けにくいことが最大の特徴です。分けにくさゆえに、相続で揉めてしまうことがよくあります。
マンションを相続する際は、まずは兄弟の双方で不動産は平等に分けにくいということを認識し合うことが適切です。その上で、平等性を重視したい場合には換価分割、継続利用を重視したい場合には現物分割を選択していきます。分割方法は手段に過ぎませんので、分け方を決める前に何を重視したいかを先に話し合うことをおすすめします。
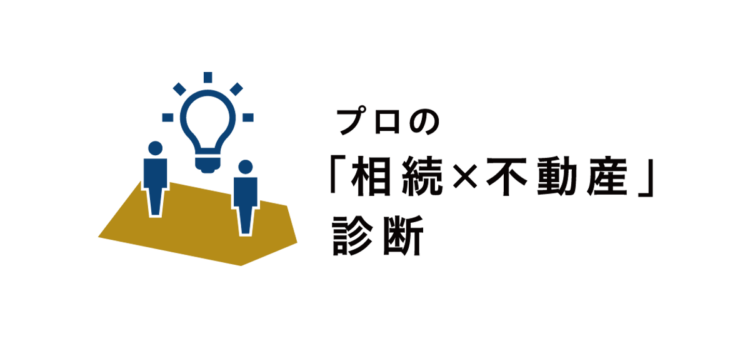
東急リバブルの相続サポート
不動産相続のことなら、東急リバブルの相続サポートにお任せください。
不動産のプロと相続のプロがトータルサポートいたします。
プロの「相続×不動産」診断はこちら








