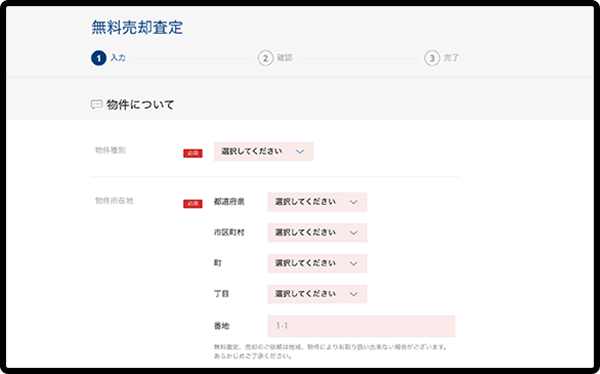専門家
コラムVol.17
不動産価格が上昇する理由と建築工事費の
動向から見る今後の不動産価格
 COLUMNIST PROFILE
COLUMNIST PROFILE
吉崎 誠二
不動産エコノミスト
社団法人 住宅・不動産総合研究所 理事長
不動産価格が上昇する理由
22年半ば以降、全国的に様々な「物の値段」が上昇していますが、不動産価格は、金融緩和政策が始まった2013年頃からほぼ一貫して価格上昇を続けています。
不動産価格の上昇の背景には、3つの側面があります。1つは、供給が多くない中で需要が増えた事、2つ目は土地や建築資材、あるいは建設労働費といったコストが上昇した事。これらに加えて、3つ目は、金利が史上最低水準にまで下がった事です。自宅用の不動産購入や投資用不動産購入(投資)においては、ほとんどの方が金融機関から借り入れを行い購入します。融資を受けて買う場合の不動産の価格は、「不動産価格+利息」ということになります。つまり、金利が低くなるということは総額が低くなることですから、「お買い得感」がでるわけです。(さらに、自宅購入の場合は条件を満たせば、最大総額400万円を超える住宅ローン減税=実質国からの支援金、があります。)
これらの逆のことが起こると、価格は下落します。

物価の上昇はなぜ起こるのか
日常生活においても物価高が実感されるようになってきました。スーパーなどで食品を買う時、あるいは飲食店で食事をする時、その他タクシーに乗っても実感します。
そもそも、不動産に限らず一般的に物価の上昇はなぜ起こるのでしょうか?
理論上、物価上昇は、「需要が増えた時」もしくは「供給量が減った時」に起こります。学生の時に習ったDS曲線を思い出してください。(図1)

左上~右下の曲線のD(需要)と左下~右上へのS(供給)の交点がP(価格)となります。
需要が増えるということは、Dの曲線が右上にスライドすることになります。この際にSの曲線(供給量)に変化がなければ、価格上昇が起こります。多くの方が「欲しい」と行動を起こし、売る側は値上げを行うわけです。年末年始の繁忙期のホテルや飛行機料金などが分かりやすいでしょう。また、一気に需要が増えた時に、生産が追い付かないような場合や生産調整を行えば、価格上昇が起こります。近年のガソリン価格上昇の背景には、こうした要因がありました。
逆に、供給が減り需要が確保されていれば、価格上昇が起こります。近年不漁と言われている秋刀魚の価格、天候不良時の生鮮食料品の価格などがいい例です。また、供給確保が難しい山頂などのレストランでの食事は、「高いな」と感じることが多いと思います。
このように需給のバランスが崩れ、需要>供給の時に物価は上昇します。
高水準続く東京都区部消費者物価指数
物価水準を推し量る公的な指標が「消費者物価指数=CPI」です。
公的な消費者物価指数には、全国消費者指数と東京都区部消費者物価指数の2つがあります。このうち、東京都区部消費者物価指数は、全国消費者物価指数より先に集計・公表されますので、先行指標となっています。
1月10日に総務省より東京23区の2022年12月分の消費者物価指数が発表されました。これによれば、天候による変動が大きい「生鮮食品を除いた指数=コア指数」が、前年同月比で4.0%上昇しました。4%台の上昇となるのは、1982年4月以来40年8か月ぶりの高い水準となります。

主な上昇要因は食料品の値上げで、「生鮮食品を除く食料」だけをみれば、前年同月比7.5%も上昇し、これは1976年8月以来46年4か月ぶりの高水準となりました。また、あわせて発表された、2022年年間の消費者物価指数は、「生鮮食品を除いた指数」が前の年と比べて2.2%(速報値)上昇しました。2.2%の上昇率は2014年以来8年ぶり、消費税率引き上げの影響を除くと、バブルが終わった直後の1992年以来30年ぶりの水準となります。
物価の上昇と同じように建築費も上昇しています。
先に述べたように、建築費の上昇は、不動産価格の上昇要因の1つです。

円安でさらに加速する建築費の上昇
図2は、国土交通省が毎月公表している「建設工事費デフレーター」の中から、住宅総合を抽出したもので、2011年からの推移を示しています。この間に、建設工事費の上昇が顕著な時が何度かありましたが、目立つのは、2021年の春ごろからの大幅上昇です。これは世界的に木材価格が上昇した「ウッドショック」のためです。ウッドショックの背景は、新型コロナウイルスによりアメリカ等の先進各国で住宅需要が増えたことがあげられます。また、日本でもリモートワークが進み、郊外に移住したり、自宅をリフォームしたりする人が増えたことに加えて、史上最低水準の低金利であることで、住宅需要が増え、住宅に使用する木材の需要は急増しました。
一方で、世界各地で大規模な山火事が起こるなど、原材料が不足するなどして、供給量は少なくなっていました。

このように需給のバランスが崩れたことで世界的に木材価格が上昇し、その影響を日本も大きく受けることになりました。2022年以降は、これらに加えてエネルギー価格の上昇と円安の影響で輸入資材価格が更に上昇しました。グラフをみれば、2022年半ば以降は、上昇が留まっていますが、依然高止まりが続く2015年に比べると25%程度高い状況です。
この先は、円安傾向がおさまり、原油価格も落ち着きをみせていますが、その一方で、労働人件費の上昇が進行しているため、建設工事費デフレーターは、引き続き高い状況が続くでしょう。
金利上昇でも不動産価格は下がらない?
この先、金利の上昇可能性が高くなってきました。金利の上昇は価格下落の可能性をもたらします。しかし、冒頭で述べたように、価格上昇下落の理由は、金利以外にも需給のバランス、建築費工事費なども要因となります。建築費は下がる可能性はしばらくなさそうで、需給のバランスもいまは均衡状況です。
こうしたことから、不動産価格はしばらく横ばいが続くものと思われます。
 COLUMNIST PROFILE
COLUMNIST PROFILE
吉崎 誠二
不動産エコノミスト
社団法人 住宅・不動産総合研究所 理事長
早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。
立教大学大学院 博士前期課程修了。
㈱船井総合研究所上席コンサルタント、Real Estate ビジネスチーム責任者、基礎研究チーム責任者、(株)ディーサイン取締役不動産研究所所長を経て現職。不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーションなどを行うかたわら、テレビ、ラジオのレギュラー番組に出演、また全国新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演を毎年多数行う。
著書:「不動産サイクル理論で読み解く不動産投資のプロフェッショナル戦術」(日本実業出版社」、「大激変 2020年の住宅・不動産市場」(朝日新聞出版)「消費マンションを買う人、資産マンションを選べる人」(青春新書)等11冊。様々な媒体に、月15本の連載を執筆。
資格:宅建士
レギュラー出演
◇ ラジオNIKKEI「吉崎誠二の5時から“誠”論」(月~水: 17時~17時50分)
◇ 「吉崎誠二のウォームアップ830」(月: 8時30分~ニュース解説番組)
◇ テレビ番組:BS11や日経CNBCなどの多数の番組に出演
吉崎誠二公式サイト http://yoshizakiseiji.com/
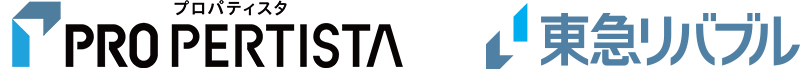

 買う時も、売る時も、
買う時も、売る時も、