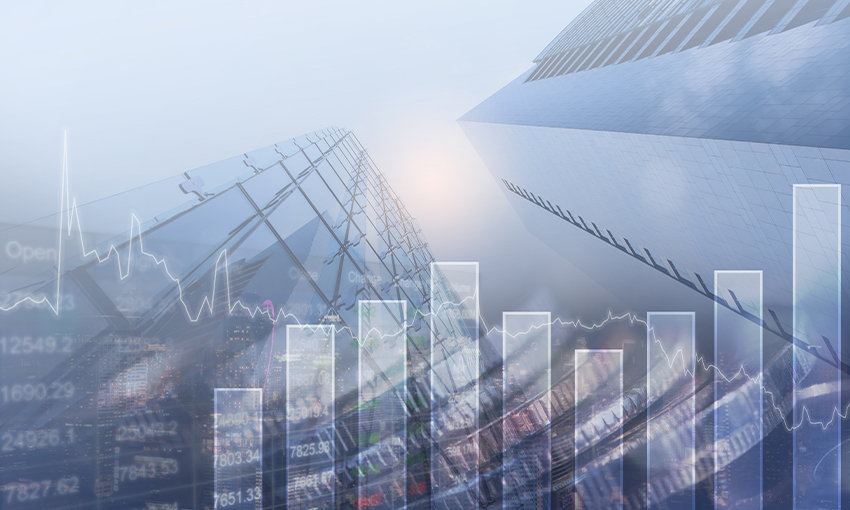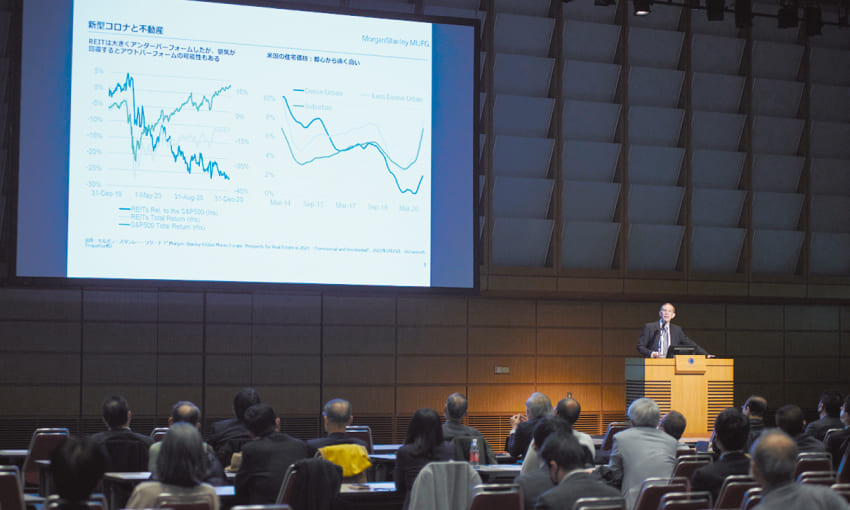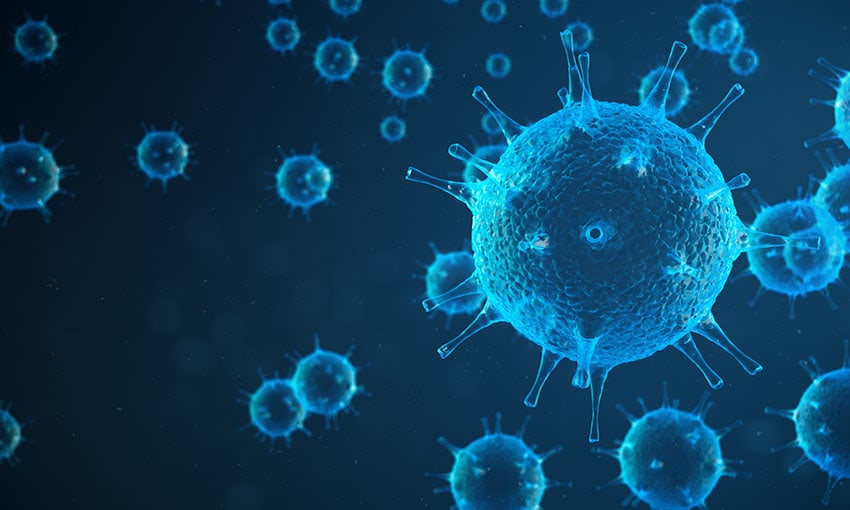2024年不動産動向~オフィス空室率からみるオフィス需給予測と日米の違い~
#不動産投資
#オフィス
#海外
#リモートワーク

日本ではオフィス回帰により空室率が低く維持されており、今後も安定した推移が予想されますが、アメリカのオフィス需要は回復しておらず高い空室率がつづいています。
なぜ、アメリカでは高く日本では低く抑えられているのか、オフィスマーケットを取り巻く環境や、働き方の違いによる日米の違いに着目しその原因を分析します。
さらに、2024年は三大都市におけるオフィス新規供給がつづき、景気回復と海外からの投資が期待される今後のオフィスマーケットの見通しを解説します。
目次
1. オフィス空室率から読み解く不動産市場

コロナ禍が収束し、国内の経済活動はコロナ前の状況に戻っていると読み取れますが、オフィスマーケットに着目すると三大都市における平均空室率は、コロナ禍ピーク時より若干の改善がみられています。
一方、アメリカのオフィス空室率は、コロナ禍直前に15%を切っていたものがコロナ禍の拡大とともに上昇しました。その後、収束の見通しが立ち始めたにもかかわらず、さらに上昇し2023年末には20%近い空室率で高止まりしています。
この章では日本とアメリカにおけるオフィス空室率の違いに着目しつつ、その背景を分析します。つづいて地価上昇や建設コストの上昇など、見直しが迫られるオフィス賃料について解説します。
1.1. 日本のオフィス市場は空室率が安定
日米の空室率を比較するにあたり、まず日本における空室率の推移を確認します。

三大都市におけるビジネス地区の空室率は、コロナ感染者の最初の確認があった2020年の第1四半期には平均で1.87%と極めて低い状態でした。
感染拡大とともに空室率は上昇し、ピークは2022年第二四半期の平均5.80%(月次では4月が5.87%がピーク)になっています。その後ゆるやかに改善、2024年2月が5.28%となり、緊急事態宣言が実施されていた2021年後半以降、5%台を維持しながらも悪化することなく現在に至っています。
日本の空室率改善がゆるやかに推移している原因として、2022、2023年に大阪および東京でオフィスの大量供給があります。既存ビルにおける二次空室の発生がオフィス回帰による需要増を相殺したため、空室率の改善がわずかになったと思われます。
また、空室率のピークが四半期平均で5.8%となっていたことは、テレワークの普及率が比較的低かったことも影響していると言えるでしょう。
日本の空室率が低い水準で維持されてきた背景として、もう1つ加えておくべきことがあります。
日本はコロナ禍による極端な行動制限、つまりロックダウンを実施しなかったことがあげられます。企業活動は比較的自由に継続することができ、コロナによる打撃を受けた産業も比較的少なく、オフィス需要を縮小させる要因があまりありませんでした。
さらに、2022年から3年間連続で上昇した地価に見るように、景気回復への期待と海外からの投資対象としての評価がますます高まっている現状が、低い空室率を維持している要因と言えるでしょう。
1.2. 高止まりするアメリカの空室率
次にアメリカの空室率についてみていきます。下図は「Cushman & Wakefield社」のデータを基にアメリカ全体の空室率推移をグラフ化したものです。

出典:Cushman & Wakefield「U.S. OFFICE REPORTS」より作成
データは2022年からのものになりますが、アメリカがコロナ収束を宣言したのは2022年9月です。コロナ収束にもかかわらずオフィス空室率はさらに上昇し、2023年第1四半期には18%を突破しています。
日本とはまったく異なる状況が起こっていますが、大きな要因はテレワークの普及と言えそうです。
テレワークはアメリカが起源とされ、そのはじまりは1970年代と言われます。もちろんこの頃はITなどまだない時代であり、あまり普及はしなかったそうですが、2001年の同時多発テロの時にはテレワークのメリットが注目されたと言われます。
コロナ禍が経済活動に影響を与えはじめた時点において、アメリカではすでにテレワークが普及しており、オフィス需要は日本ほど高くはなかったと予想できます。また、コロナの収束後もオフィス需要が回復しない要因として、金利上昇や景気減速への懸念があり、企業活動が消極的になっている可能性もあるでしょう。
以上のようにアメリカの高い空室率の要因は、コロナ禍において推進されたテレワークがコロナの収束によっても継続していることがあげられています。さらにeコマースの拡大がオフィスや商業施設の需要を減少させたことも要因と言えるでしょう。
1.2.1. 日米におけるテレワーク実施率の違い
次に、先に触れた「テレワーク実施率」について、日米の違いを少し掘り下げてみます。
テレワークの実施状況について、詳しく調査を実施しデータが公表されている東京都と、アメリカの公的データに基づき比較してみます。
下図は東京都のテレワーク実施率の推移を表したものですが、コロナ収束のめどが立った2023年1月頃には約51%の実施率となっています。ピークは2021年8月の65.0%でした。

最新の実施率としては2023年12月の46.1%という結果です。東京都の調査における実施率は週1日以上の実施が該当し、週5日を実施する完全リモートは約10%となっています。
なお、この完全リモートの割合はコロナの収束めどが立った2023年1月頃も同様と思われます。
対してアメリカではコロナの収束めどが立った2022年8~9月時点で、常時テレワークを行った割合が27.5%と米国労働統計局は発表しており、東京都との違いは2.7倍に及ぶことがわかります。
以上のように日本とアメリカとではテレワーク実施率に違いがあり、その結果が空室率の違いとして表れています。さらに、日本においては「人とのつながり」や「対面の良さ」を評価する意識の違いもあり、心理的な理由からオフィス需要が回復している面もあると言えるでしょう。
1.3. 懸念される賃料上昇傾向
空室率の上昇は賃料を下落させる要因です。供給過多になると必然的に空室率は上昇し、競争が激しくなると賃料に下落圧力が働き、その結果収益性が低下するといった悪循環が生じます。
収益性の悪化はオフィスオーナーにとって投資意欲を減退させるものですが、一方で賃料を上昇させる環境変化が生まれています。
1つは地価の上昇です。新規のオフィス供給において土地の取得を含む場合は、投資額に占める土地取得費の割合が増加します。さらに、建築資材の高騰と2024年問題とも言われる人件費の高騰がオフィスビル建設コストを引上げ、賃料上昇傾向を強くさせると予想されます。
建築コストについて付け加えると、2024年2月の事務所建築費指数は130(2015年を100)と前月比プラスとなっており、今後は人件費がさらに上昇する見込みです。
また、日銀がマイナス金利の解除を行い金利上昇が視野に入りました。今後金利の上昇により返済負担が増加するオーナーは、賃料の見直しをせまられることになります。
ただし、既存ビルのオーナーにとって賃料見直しはプラス思考で考えることもできます。新築オフィスの賃料上昇は必至ですが、賃料相場は全体として上昇傾向となり、利回りやキャッシュフローの改善が期待できる可能性もあるでしょう。
2. オフィスマーケット2024年の見通し

2024年のオフィスマーケットを予測するにあたり、次の3つの視点から考察します。
- 三大都市における新規供給
- 経済回復と日本への投資
- 失業率の改善と起業率の上昇
いずれの視点もマクロ的なものであり、オフィスマーケットの状況は月次レポートなどで確認することが望ましいです。現時点においては、全体を捉える参考としてください。
2.1. 三大都市における新規供給がつづく
東京、大阪、名古屋ではオフィスビルの新規供給がつづきます。とくに東京は約22万坪、大阪は約24万坪と大量供給が行われます。
大量供給は短期的な空室率の上昇を招きますが、築古ビルからの移転などで空室増加は既存ビルにおいて深刻となり、廃業や用途転換などオフィス市場からの撤退が増加すると全体の空室率は低下していきます。
このような動きは築浅ビルと築古ビルの二極化を促進させる一方、立地条件のよい築古ビルではリノベーションや建替えによる再生事業が活発化する可能性もあるでしょう。
全体としては以上のような傾向が予想されますが、主要市場である東京に焦点をあてるとエリアにより違いが生じている状況もあります。
2023年末時点における都心5区の空室率は「丸の内・大手町」エリアと「六本木・赤坂」エリアとで数ポイントの違いがあり、「丸の内・大手町」は空室率が2.1%と5.9%低く、平均賃料においては約41,000円と8,000円ほど 高くなっています。
さらに、空室率の低いエリアであっても築年数やオフィスの質から空室率の高いビルもあり、ビル同士の差別化や二極化が生まれていることにも注目しなければならないでしょう。
2.2. 経済回復と日本への投資
2024年に入り日経平均株価はバブル崩壊後の最高値を更新しつづけ、3月には4万円を超えて史上最高値の更新もありました。
半導体関連株が上昇を見せていますが、逆に値下がりする銘柄も半分以上あり、必ずしも日本経済全体が右肩上がりとは言えない状況です。
一方、春闘における各企業の回答結果は満額回答が多く、上場企業で賃上げの流れが形成されています。今後は中小企業への波及が見られるかが課題です。
現在の物価上昇を上回る賃上げが実施されると日本経済への影響は大きく、企業活動は活性化されオフィスビル投資も継続する期待が持てます。
また、日本は海外直接投資信頼度において、昨年4位のドイツを抜き3位となっています。アメリカ、カナダに次ぐ信頼度の高さは、今後の再開発や築古ビル再生事業などへの海外資本投資が、さらに活発になると予想できる要因となるでしょう。
2.3. 失業率の改善と起業率の上昇
空室率は失業率に遅行するとも言われます。つまり、失業率が高くなると空室率は上昇し、失業率が低くなると空室率も低下します。
現在、日本の失業率は2.4%と低い水準を維持していますが、令和5年12月の有効求人倍率は1.27、新規求人倍率は2.26となっており、売り手市場の状況となっています。求人状況から見ても失業率の低い水準は今後もつづく見通しです。
失業率と同様に空室率に連動する指標があります。それは起業率であり、起業率が高まると空室率は低下します。
現在、日本の起業率は欧米と比較し低くなっていますが、終身雇用の崩壊や転職率の上昇は、起業機会を創出する可能性もあり、今後の日本の起業率は上昇すると期待できそうです。
しかしながら短いスパンでの期待は難しく、将来の潜在需要として捉えるほうがよいと考えられます。
3. 2024年のオフィスマーケットは安定に推移
2024年は三大都市において、新規オフィスの供給がつづきます。地方の主要都市でも比較的安定した状況であり、新規供給があってもオフィス需要は維持され、空室率の急激な悪化はないと見てよいでしょう。
物価上昇に見合う賃金上昇が今後中小企業にも波及し、全体としての日本経済回復状況が確認できるようになると、オフィス需要は持続し経済拡大を期待する局面となるでしょう。
そのため、アメリカと比較すると非常に低い水準にある日本の空室率は、2024年も安定して推移すると思われます。
懸念されるのは金利の上昇です。借入金の返済額増加による賃料の上昇と、テナント企業の金利負担による収益減が、家賃の負担感を増大させる結果になります。その結果、賃料の下押し圧力が生まれ、オフィスビルオーナーの収益性が悪化するといったシナリオが考えられます。
30年以上「金利のない日本」でしたが、今後は金利の上下が企業経営に大きな影響を及ぼします。2024年はそのターニングポイントになることでしょう。
関連記事:2024年の不動産市場はどうなる?現状と今後の見通しを分析
一級建築士、宅地建物取引士
弘中 純一 氏
Junichi Hironaka
国立大学建築工学科卒業後、一部上場企業にてコンクリート系工業化住宅システムの研究開発に従事、その後工業化技術開発を主体とした建築士事務所に勤務。資格取得後独立自営により建築士事務所を立ち上げ、住宅の設計・施工・アフターと一連の業務に従事し、不動産流通事業にも携わり多数のクライアントに対するコンサルティングサービスを提供。現在は不動産購入・投資を検討する顧客へのコンサルティングと、各種Webサイトにおいて不動産関連の執筆実績を持つ。