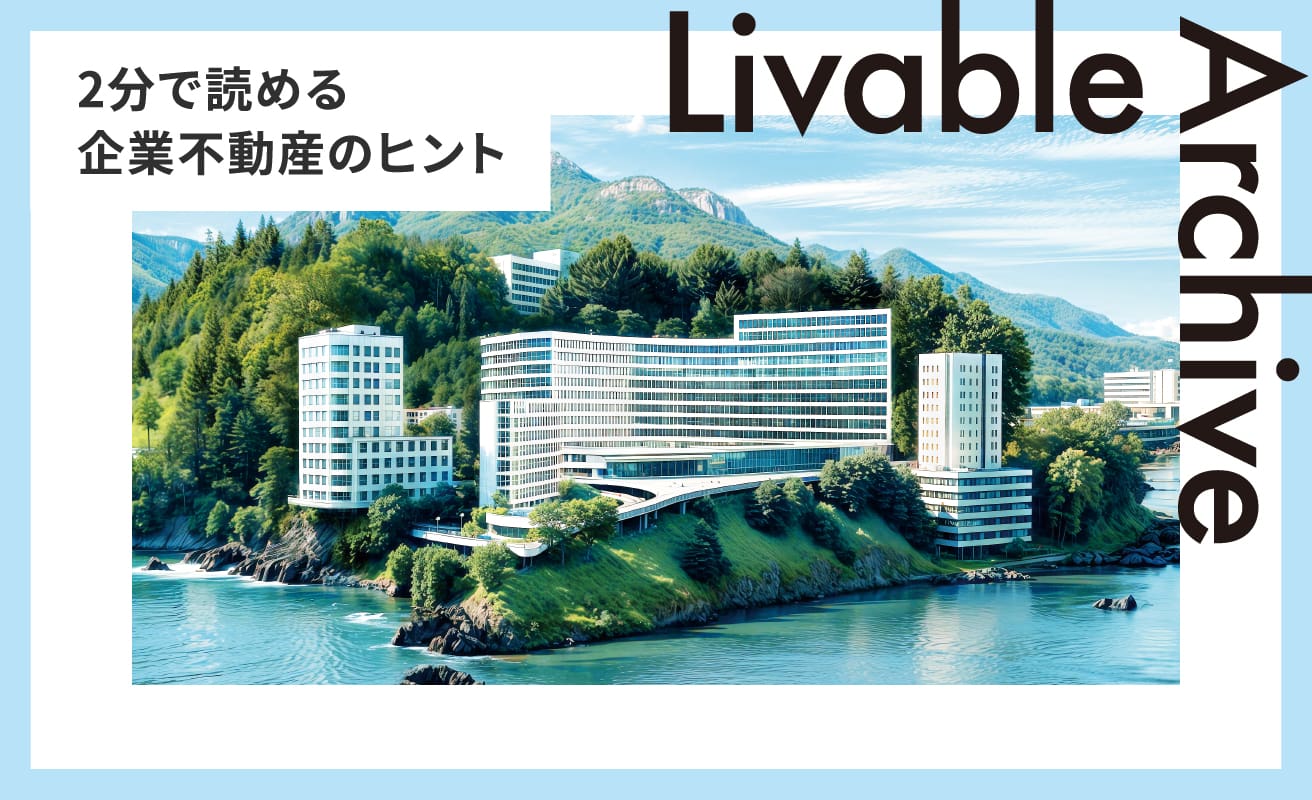オフィスマーケットの需給状況と今後の見通し
#オフィス
#全国
#事業用不動産

2023年6月のオフィスビルに関する需要と供給状況は、首都圏以外の大都市圏では空室率の改善が見られますが、首都圏とくに都心5区は空室率が上昇しています。都心では大規模オフィスビルの供給がつづき競争が激化、古いビルから移転する企業も増え二次空室が問題になると考えられ、古いビルの再生事業も今後は課題として大きくなる可能性があります。そこで、本記事では今後のオフィスマーケットの見通しについて解説します。
目次
1. データから見るオフィスマーケットの現状

直近1年間の3大都市圏におけるオフィスマーケットについて確認する前に、2019年以降の4年間の推移を確認します。
供給量は、東京では2019年に約30万m2の供給、2020年には約53万m2と大量の新規供給があり、その後も15万~16万m2の供給がつづいています。
名古屋は2021年に約6万m2が供給されています。大阪は2020年、2021年と約2万m2前後の供給でしたが、2022年には約11万m2の供給が行われました。

東京では供給がつづいたため、次のように空室率の増加と家賃の下落が見られます。名古屋、大阪も東京ほどではありませんが、空室率が増加しています。しかし平均家賃は名古屋、大阪ともほぼ横ばいが続いています。


つづいて2022年6月以降の最近1年間の状況について供給量と空室率の変化をみていきます。
東京(都心5区)は2か月連続で空室率が増加しましたが、大規模オフィスビルの竣工による供給量の増加が影響しています。

名古屋(主要4地区)は供給量に変化はなく空室率は横ばいとなっています。
大阪(主要6地区)は空室率がわずかに改善しています。館内増床や拡張移転などがあったためであり、供給量に変化はありません。
過去4年間と最近1年間の推移から次のポイントをあげることができます。
- 東京は空室率が上昇傾向にあったが、最近1年間ではほぼ横ばいとなっている
- 名古屋は2021年まで空室率の上昇があったがその後改善し、現在は横ばいがつづいている
- 大阪は2022年まで空室率が上昇傾向だったが最近1年間は改善傾向になっている
- 平均家賃は東京が低下傾向だが、名古屋、大阪は横ばいとなっている
2. オフィス市場に影響を与える最近のトピックス

オフィス市場の状況を見通す上で、影響を与えると思われる最近のトピックスを紹介します。
オフィスビル大手「森ビル株式会社」の市場動向調査によると、東京では2020年に大規模オフィスビルの供給が20件あり、延床面積は179万m2となっています。2023年にも15件126万m2の供給が予定されており、延床面積10万m2以上の大規模オフィスビルの割合は80%に及ぶと言われます。
さらに2025年には20件136万m2の大規模オフィスビルの供給もあり、大規模化と都心部への集中が顕著になると予想され、エリアとしては虎ノ門、品川、赤坂、六本木での増加が予定されています。
一方で、オフィスビルの供給増加により空室率の上昇が懸念されます。需要動向としては、都心エリアおよび大規模オフィスビルに対する需要回復が見られ、ハイグレードなオフィスへのニーズが高まっています。
したがって大規模オフィスビルが供給されるエリアにおいては、今後の供給増加により空室率が上昇する影響は少ないと見込まれています。
2.1. 変化するオフィス需要
新規の大規模オフィスビルの供給増加があっても需要が見込め、空室率の上昇は少ないと予測される背景にはオフィス需要の変化があります。
コロナ禍を契機として普及したテレワークは、オフィスに出勤する日とテレワークする日を組み合わせた「ハイブリッドワーク」を生み出しました。
また、テレワークを自宅ではなく「サテライトオフィス」で行うといった多様な働き方も生まれています。
オフィスレイアウトにも変化があり「フリーアドレス」を導入する企業や、カフェコーナーなどを設置する企業など、働き方の変化を積極的に採用するケースが見られます。さらに、さまざまな付加価値を備えた高機能ビルを求めるケースもあります。
このような変化は既存の古いビルでは対応できない場合もあり、新しい考え方に基づくビルは変化したニーズを取り込むことができるでしょう。
さらに大規模オフィスビルでは区画を小さくした募集方法もとられており、これまで中小規模のオフィスに入居していた企業が、大規模オフィスビルに移転しやすい条件が整っていることも、相対的に新規の大規模オフィスビルについては空室率が低く納まる要因になるでしょう。
3. 今後の見通し
今後のオフィスビルの需要と供給の見通しとしては、次のようなポイントをあげることができます。
【供給面でのポイント】
- 大規模オフィスビル同士の競争が激化
- 新築ビルの増加により既存ビルでは二次空室が増加し、築年数の新しいビルと古いビルでは空室率に格差が生まれる
- 東京23区では2023年のビル供給量が2022年の2.8倍となる
- 東京は2025年にも136万m2の大規模オフィスビルの供給がある
- 名古屋では2023年から2024年6月までに25万m2の供給が集中
- 大阪では2024年に梅田エリアで60万m2の供給が集中
新規供給のビルに占める大規模オフィスビルの割合が増えるとみられ、さらに高機能・好立地のビルほど人気が高く、ビル同士の競争は激しくなり選別がされるようになるでしょう。
新規ビルへの移転が多くなると既存ビルでは二次空室が増加、さらに二次空室へ移転する企業が生じると三次空室が増加するといった状況まで考えられます。現状において空室率が高いのは築21~30年のビルであり、築浅のビルは大規模オフィスビルで空室率が低くなっています。
3大都市圏を比較すると、名古屋の新規供給は2024年7月以降で小規模な供給がありますが、東京、大阪ではまだまだ大規模なオフィスビルの供給がつづき、競争の激化は避けられないと言えるでしょう。
【需要面でのポイント】
- オフィス需要の意識調査ではオフィス面積の拡張が減少し、縮小が増加
- ニーズの多様化が生じており、対応できない物件は空室率が悪化する
- 好立地なオフィスビルへの移転が増加する
前述した「森ビル株式会社」の市場動向調査では、コロナ前に比べてオフィスの拡張を希望する企業は減少していると言われています。オフィスの質的変化で見たように、必ずしも「スペース」を必要
とする企業は少なく、オフィスに対するニーズが多様化しており、既存ビルを含めた供給量全体を満たす需要の存在には疑問が浮かびます。そのため今後の景気回復があったとしても、オフィスの需要は拡大しない可能性があり、多様な用途に対応できないビルはテナント募集に苦戦を強いられるかもしれません。
3.1. ビジネスモデルとしてのビル再生事業
新しい働き方に対応できないビルや築年数の古いビルは、オフィス市場からの撤退を余儀なくされる可能性があります。
立地条件のよいビルに関しては建替えが選択肢となりますが、建替えまで踏み切れない場合は解体し別の用途に使用するか、再開発を企画するデベロッパーへ土地を売却するといった選択肢もあるでしょう。
賃貸不動産としての活用を図るにはリノベーションなどによる「ビル再生」が有効な方法になります。すでにデベロッパーや建物メンテナンス事業を主とする企業が、ビルやマンションの再生事業に進出しています。
古いビルのストックは再生事業やビル跡地の転用など、不動産業にとってビジネスチャンスを創出する基盤とも言え、ビル再生事業をビジネスモデルとして確立する動きも出てくると思われます。
4. 競争激化がつづくオフィスマーケット
3大都市圏では今後2~3年間で新規のオフィスビル供給がつづきます。しかも大規模オフィスビルの割合が高く競争が激化すると同時に、既存ビルからの移転による二次空室増加が懸念されます。
オフィス需要にも変化が生じておりフリーアドレスの採用や、カフェコーナーを設けたオフィスなど、新しいスタイルがニーズとして顕在化しています。さらにサテライトオフィスやハイブリッドワークの採用などにより本社オフィスの縮小傾向が見られ、オフィス需要そのものが停滞する可能性を指摘する声もあります。
企業によるオフィスビルの選別は空室率が低い水準で維持できるビルと、空室率が悪化し経営が苦しくなるビルの二極化を進行させ、オフィスマーケットからの撤退を余儀なくされるビルも生まれるのではないでしょうか。
今後3大都市圏において、2025年に東京で136万m2、2024年に名古屋で25万m2、同じく2024年に大阪で60万m2の新規供給が予定されており、大きく変化したオフィスマーケットの姿を見ることになるでしょう。
一級建築士、宅地建物取引士
弘中 純一 氏
Junichi Hironaka
国立大学建築工学科卒業後、一部上場企業にてコンクリート系工業化住宅システムの研究開発に従事、その後工業化技術開発を主体とした建築士事務所に勤務。資格取得後独立自営により建築士事務所を立ち上げ、住宅の設計・施工・アフターと一連の業務に従事し、不動産流通事業にも携わり多数のクライアントに対するコンサルティングサービスを提供。現在は不動産購入・投資を検討する顧客へのコンサルティングと、各種Webサイトにおいて不動産関連の執筆実績を持つ。