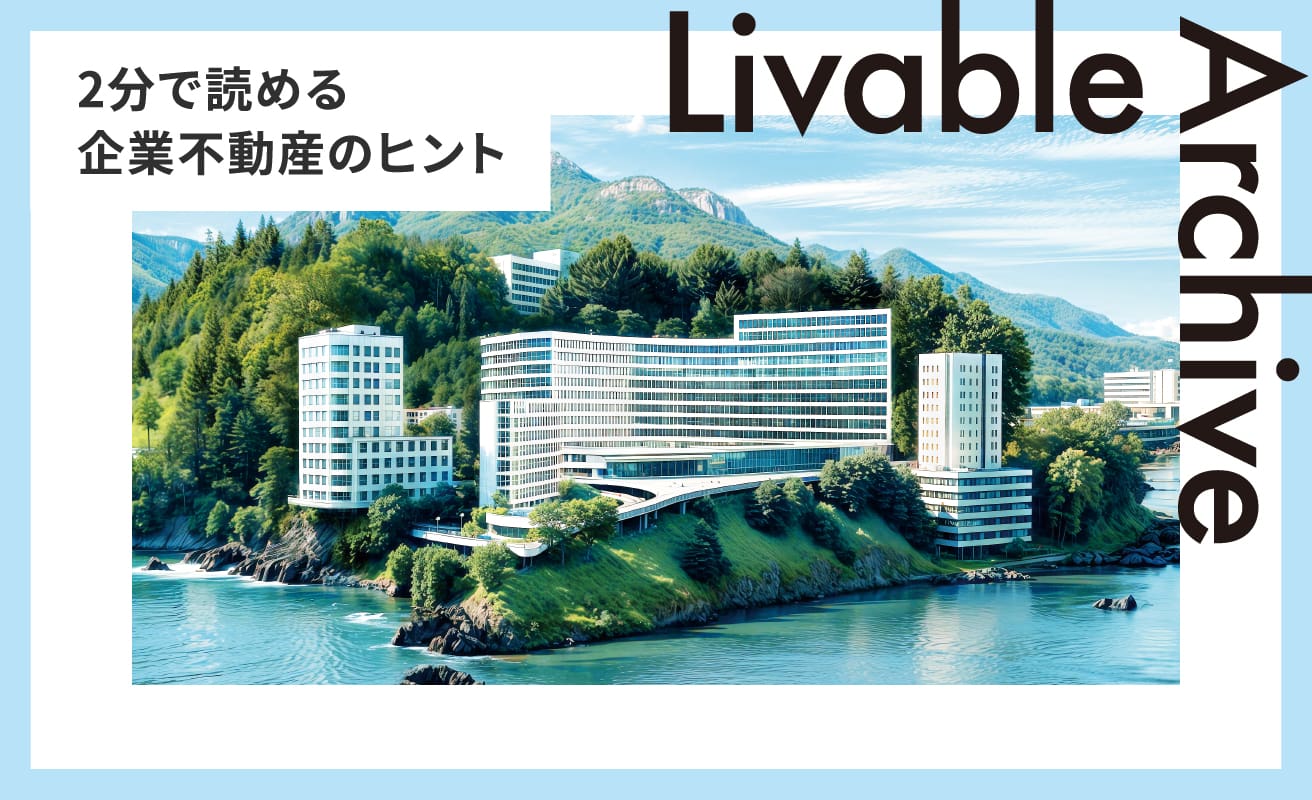2025年の不動産市場はどうなる?現状と今後の見通しを分析
#不動産投資
#事業用不動産
#不動産種別

2024年は3年連続で地価が上昇し、オフィスビルの新規供給やホテルの新規開業など、活発な不動産投資が行われた1年でした。オフィスビルでは、空室率が改善し賃料が上昇するなど収益性も高まっています。
2025年は不動産市場にとって政策金利の上昇が大きな注目点となりますが、日米のトップ交代が経済環境を変化させると予想され、日本経済全体の動きが金利以上に不動産市場に影響を及ぼす可能性もあります。
この記事では、予測の難しい局面の中で、現在考えられる2025年の見通しについて解説します。
目次
1. 不動産市場の現状と見通し:要約

【不動産市場の現状】
- 3年連続の全用途における地価上昇となった
- 首都圏のマンション市場に高止まり感があり成約率が低下
- オフィスは空室率が低下し賃料の上昇が続いた
- 商業施設は三大都市圏にショッピングセンターの開設が集中
- ホテルでは外資系ホテルの開業が目立つ
【不動産市場の見通し】
- 住宅市場は新築物件のコストが上昇し中古市場が拡大
- オフィスは新規供給が続くも空室率は低い水準で推移
- 商業施設の都心部への集中が継続し都心回帰を促進させる
- 外資系ホテルの開業ペースは変わらず活発に
- 物流施設は供給過多により空室率の上昇も懸念される
2. 2024年の不動産市場振り返り

2024年の不動産市場は「地価公示価格」が3年連続上昇し、さらに「基準地価」でも上昇傾向が続いているのが確認されました。2024年も地方4市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)が三大都市圏を上回る上昇率となりました。
しかしながら地方4市は、公示価格、基準地価とも前年の上昇率より低下し、三大都市圏は前年を上回る上昇となっています。地方4市において地価を急上昇させた要因が減少し、今後は三大都市圏の上昇率水準に落ち着くのか注目されるところです。

アセット別では、首都圏の中古マンション市場において、2024年3月に成約件数が前年比のピークを記録しましたがその後低下しています。またm2単価は7月まで上昇したものが、8月に下落しており流動性の低下が懸念されます。
オフィス市場は三大都市において、空室率の低下と賃料の上昇が見られ堅調と言えます。オフィス回帰が浸透しコロナ前の状況にほぼ戻った感があります。
商業施設は三大都市圏においてショッピングセンターの新規開設が多く、大型施設も三大都市圏に集中しています。都心部への人口流入と再開発による利便性の高さが、都心部の魅力を高めた結果でしょう。
ホテルはインバウンドの本格的な回復により、新設ホテルとりわけ外資系ホテルの開業が目立つ1年となりました。一方、人手不足が原因となり稼働率を上げられないといった課題も浮かんでいます。
物流施設は新規供給の増加による移転需要が落ち着き、空室率は10%前後まで上昇していますが、一部では5%以下になるエリアもあり格差が生じています。
また、不動産市場に影響を及ぼす景気動向は、2024年3月に日経平均が最高値を更新し、デフレ脱却と景気回復に向けた動きが見られるようになりました。しかしながら日米関係を含めた国際環境が変わりつつある中、不動産市場が変化する要因もいくつか指摘されており、今後の動向に注目が必要でしょう。
3. 日米トップ交代による不動産市場への影響
2024年10月1日石破政権が誕生し、2025年1月20日にはトランプ政権が誕生しました。日米のトップ交代は不動産市場にどのような影響を与えるのでしょう。
少数与党として誕生した石破政権は、思い切った経済政策を打ち出すことは難しいと考えられ、2025年7月の参議院選挙までは政権維持が最優先事項となるでしょう。
当面の経済政策として注目されるのは、手取り増加を目的とした「減税」です。収入増により消費が上向くと経済全体を押し上げ、企業の投資が増加し不動産市場によい影響を与えます。逆に手取り増加分が物価高と相殺されることや、消費に廻らず貯蓄されると再び以前のデフレ経済に戻ってしまう懸念もあります。
一方、石破政権の目玉とも言える地方創生に関しては、地方におけるインフラなどへの投資が増加する可能性が高く、不動産市場が活性化する期待が持てそうです。
トランプ政権は日本と異なり、非常に強い政権基盤のもとに誕生となりました。政策の基本方針は「MAGA」であり、簡単に述べると偉大なアメリカを再び復活させることです。そのための大きなテーマとしては「減税政策」と「関税政策」が考えられます。
日本に与える影響は「関税政策」が大きなものですが、当面は対中関税の引き上げが可能性として高く、対日関税策の実現は2026年になるものと見られておりまだまだ流動的です。
減税策は米国経済にプラスに働くとみられていますが、関税策が実現すると輸入品物価の上昇により経済成長はマイナスとなる可能性もあります。
本稿執筆現在、日本経済はゆるやかですが持ち直しており、日経平均株価は昨年史上最高値を更新したあと39,000円前後で推移し、円安基調も変わらずの状態です。一方、米国経済は、ダウ平均株価が昨年来の上昇基調を継続、インフレの鎮静化と個人消費の堅調により成長ペースで推移しています。しかしながらトランプ政権に移行する今後、米国経済の成り行きによっては、国内不動産に対する米国資本投資が減少する可能性もあります。
4. 経済環境による不動産市場への影響
不動産市場に大きな影響を与える日銀の政策金利は、2024年12月の利上げは見送られましたが、今後の利上げについては、1月に0.25%、その後も賃上げの状況やトランプ政権の経済政策によって、追加利上げがあるとみられています。
金利の上昇は投資コストを引き上げるため、不動産価格の下落を招く恐れがある一方、純収益の増加を図り不動産価格を上昇させるといった二面性があります。
仮に追加利上げがあるとしても小幅な利上げと考えられ、経済成長がある程度見込める場合は、不動産価格が上昇する可能性は高くなります。現在のオフィス市場の堅調な状況からみると、不動産価格の下落は当面ないと言えるでしょう。
また、不動産価格は日経平均のトレンドに近似するといった説がありますが、2014年以降の不動産価格指数と日経平均の推移を確認すると同じような動きとなっています。株価上昇により生じた利益が不動産投資に廻ることにより、日経平均株価と不動産価格が連動するとも言われます。
そのような面から、2024年10月に大きく下落する局面があった日経平均は、その後持ち直し2024年末の終値は過去最高となりました。2025年上半期までは景気回復基調が継続するシナリオが予想でき、大きな変化は生じないと言えそうです。
2025年下半期以降はトランプ政権の政策が明確になり、さまざまな影響が表面化すると思われます。国内では7月の参議院選挙の結果により、今後の経済政策に大きな変化が生じる可能性もあるでしょう。
今後、注目されるのは政策金利であり、日経平均株価の変動とともに不動産価格に変化が生じるのか、あるいは金利上昇があっても現在のトレンドが維持されるのか、2025年は不確定要素が多く見通しの難しい1年となりそうです。
5. 2025年不動産市場のアセット別見通し

2025年の不動産市場は、日本経済の回復基調の影響もあり堅調に推移すると思われますが、下半期以降は思わぬ変化が生じる可能性もあります。ここでは、現時点で考えられるアセット別の見通しを解説します。
5.1. 既存住宅の流通量が拡大し賃貸住宅市場にも変化が
2025年は住宅市場にとって大きく変化する年と言えます。省エネ基準の義務化により新築住宅のコストは上昇、さらに建築資材高騰や人手不足による労務費の上昇が住宅価格を押し上げます。
また住宅ローン金利の上昇により新築需要の縮小がすすむと思われ、今後は取得しやすい「既存住宅」の流通量が拡大する可能性が高くなると思われます。
さらに、既存住宅の需要を増加させる、もう1つの要因にも目を向けなければなりません。
それは賃貸住宅市場における「賃料上昇」です。
賃料上昇は物価上昇などによる管理コスト増加が要因と思われますが、近々実施される金利上昇への対策としての一面もあります。賃料上昇により、かねてより減少傾向と言われる「持ち家志向」に変化が生じることも考えられます。
つまり、高い賃料を払うよりも、取得しやすい既存(中古)住宅を購入しようと考える層が、一定程度増加する可能性があるでしょう。
5.2. 新規オフィス供給は続き堅調
都心部の再開発事業などでオフィスの新規供給が継続していましたが、進捗状況は終盤に入ったといえ、2023~2025年の新規供給の状況は以下のようになります。

各都市圏の状況について詳しくみていきましょう。
【東京】
都心5区では2023年に約45万坪、2024年に16万坪の竣工があり、2025年には約50万坪の新規供給が予定されています。注目される大規模ビルは港区芝浦の「BLUE FRONT SHIBAURA」に2月完成予定のS棟で、延床面積は約16万坪、オフィス、ホテル、商業施設から構成される複合ビルです。
空室率は5区平均で5%を下回っていますが、とくに千代田区は3%以下と非常に低い水準となっています。2025年も低い空室率は維持されると考えられます。
なお、新規供給以外の注目ポイントとしては、築古ビルをリノベーションにより再生し、需要の高い「高機能ビル」に再生させる動きが東京において多くなっています。そのため、築古ビルの売買が活発になっており、国内外の投資資金が集まっていると言われており、この動きは2025年も続くと思われます。
【大阪】
大阪は2024年に東京を凌ぐ大量供給がありましたが、2025年の新規供給は前年比33%程度の7.7万坪が予定されています。2024年は北区での大量供給が目立ったものの、2025年は中央区で約71, 000坪、北区が約4,900坪となっています。
注目されるビルは5月完成予定の「淀屋橋ステーションワン」。延床面積は約2.2万坪、高さ約150m、一部に店舗フロアがありオフィス貸面積は約1万坪の大規模オフィスです。もう1棟が延床面積約4万坪の「(仮称)淀屋橋駅西地区市街地再開発事業」です。オフィスと商業施設の複合ビルであり、オフィス貸面積は約23,000坪に及び2025年12月完成予定です。
2026年以降のオフィス新規供給は年間5千坪程度と少なくなり、2025~2026年が移転需要を見込めるチャンスと言えるでしょう。空室率は4%台を維持しており、賃料はゆるやかな上昇傾向が続いていますが、この傾向は続くと思われます。
【名古屋】
名古屋は新規供給が少なく5%を切る空室率が2025年も継続し、さらに3%台に低下すると予測されています。
直近では2024年12月が4.54%と前月比▽0.25%となり、7か月間連続で前月比マイナスを記録しています。また賃料は2023年12月以降連続の上昇となりました。名古屋市のオフィス需要は、リニア中央新幹線の開業期待感もあり、今後も堅調とみられています。
5.3. 商業施設で見られる都心回帰
商業施設は都心部でのショッピングセンターの開業が多くなっています。とくに三大都市圏が多く、都心回帰といった現象がみられます。
商業施設にとって人をいかに集めるかが課題ですが、国内において2つの流れが生じています。
1つは都心部への人流復活、そして2つめがインバウンドにおける富裕層の増大です。とくにインバウンドは「日本での体験」を求めてくる傾向が強くなっており、インバウンド向けのコト消費が大きな需要になる可能性があります。
このような需要に対応する商業施設として、2025年3月に「ニュウマン高輪」が高輪ゲートシティにオープン予定です。同じく3月には「グラングリーン大阪」南館に、商業施設、ホテル、MICE施設などの複合施設がオープンし、大阪万博の開催に向けて国内外からの集客が見込まれます。
また「コト消費」をコンセプトにした商業施設は都心だけではなく、インバウンドが増大している観光地においても同様であり、2023年5月以降の脱コロナにより新しい潮流が生まれたと言えるでしょう。
5.4. ホテルの新規開業が続く
2025年は外資系ホテルの開業が続きます。新規開業ホテルのうち約6割が外資系と見込まれており、2026年も約半数が外資系となります。その背景には増大するインバウンドの増加があります。
インバウンド需要では、とくに富裕層に向けたサービスの質が大きく変化しており、これまでの常識を超える高価な宿泊プランも登場しています。
2025年は大阪万博に続き、9月には「世界陸上」が東京で開催されます。大きなイベントを契機として、インバウンドが拡大する流れはしばらく続くと思われ、2030年に6,000万人の目標は現実味を帯びてくると言えそうです。
国内旅行者の動向に目を向けると、2024年の宿泊旅行者は前年比ではプラスですが、2019年比ではマイナスとなっています。
2025年は円安の影響による海外旅行の抑制基調により、国内旅行へのシフトがつづくと思われますが、賃金増の実感が広まると2019年比プラスを期待できるものと思われます。
5.5. 物流施設は空室率改善が課題に
脱コロナにより実店舗での消費が回復し、物流施設への需要は縮小傾向です。そのため空室率が目立つようになっていますが、東京では物流施設の新規供給が今後も続き、大型物流施設の市場は拡大すると予想されています。
一方、すすむ社会の高齢化に対応するため、食品や日用品を中心とした「宅配サービス」が大幅に増加する可能性があり、消費材を保管・配送する配送センターの需要が見込まれます。
宅配サービスはすでに一部のスーパーマーケットで見られたサービスですが、大手スーパーでも導入、さらにコンビニ、ドラッグストアや、さらに調剤薬局がはじめるなど、EC市場とは異なる消費・流通システムが生じています。
これらの物流形態はBtoCに該当するものですが、さらに生産者から直接消費者へと届けられるDtoC物流も生じており、加えて従来のBtoBの商品を含めた在庫管理システムが配送センターには必要です。このような新機能を持った物流施設が、今後の流れになる可能性があります。
6. 2025年の不動産市場は堅調だが後半に注意が必要
2025年はトランプ大統領の再登板で幕を開けました。国際社会の中で立ち位置が変化する米国ですが、経済面でも大きな変化を生じさせると考えられます。日本経済にとくに影響を与えるのは対日関税政策ですが、その細部が明確になるのは2025年後半だろうと言われています。
国内においては日銀の政策金利上昇が大きな影響を与えますが、景気動向により左右されるため、新政権の経済政策次第で見通しが変化します。
そのような状況下において世界の不動産市場における日本の優位性は強く、日米のトップ交代による不動産市場への直接的な影響は少ないため、前半は堅調に推移すると思われます。
しかしながら2025年後半の政治・経済状況は、これまでにないほど不確実性が高まっており、思わぬ変化が生じる可能性もあります。国際情勢を含めた広い視点で、不動産市場を分析する必要があるでしょう。
一級建築士、宅地建物取引士
弘中 純一 氏
Junichi Hironaka
国立大学建築工学科卒業後、一部上場企業にてコンクリート系工業化住宅システムの研究開発に従事、その後工業化技術開発を主体とした建築士事務所に勤務。資格取得後独立自営により建築士事務所を立ち上げ、住宅の設計・施工・アフターと一連の業務に従事し、不動産流通事業にも携わり多数のクライアントに対するコンサルティングサービスを提供。現在は不動産購入・投資を検討する顧客へのコンサルティングと、各種Webサイトにおいて不動産関連の執筆実績を持つ。